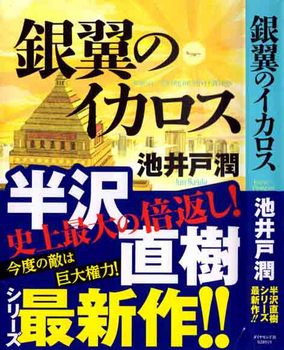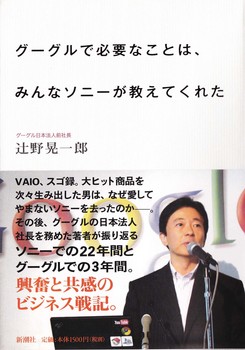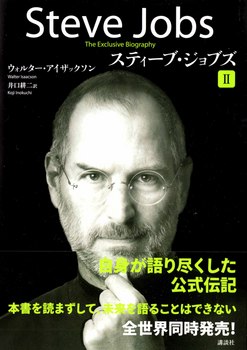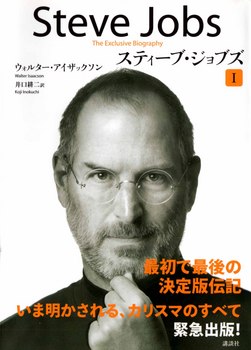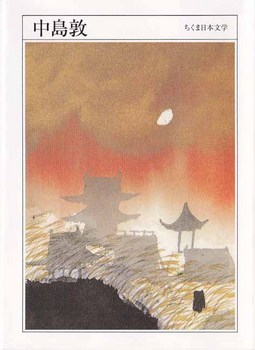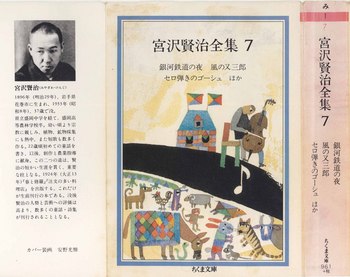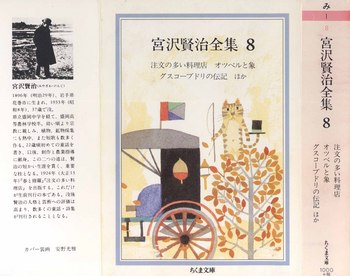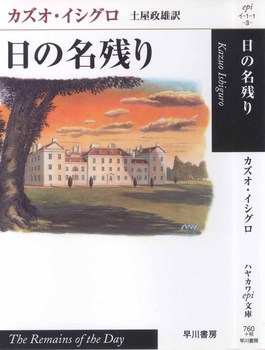池井戸 潤『銀翼のイカロス』(ダイヤモンド社、2014年) [読書]
先日、友人から半沢直樹の最新刊をもらった。今日の午後、久しぶりにのんびりしたので読み始めたが、一気に読み終えてしまった。私は、こういう劇画風の小説が結構好きだ。
半沢は東京中央銀行の営業第二部次長に復帰し、例によって難題を押しつけられる。経営危機に瀕する帝国航空の再建だ。今回の主要敵は国土交通大臣の私的諮問機関である帝国航空再生タスクフォースのリーダー乃原弁護士だが、金融庁の黒崎検査官も登場する。銀行内では既に大和田常務はいないが、紀本常務とその子分連が半沢の足を引っ張るというお馴染みの構図だ。半沢の友人、渡真利と近藤は健在だが今回は地味な脇役だ。
その代わり、重要な役回りを果たすのが富岡という半沢が入行したときの上司だ。現在は、検査部部長代理として出向を待つ身だが、なかなか味がある。もう一人は中野渡頭取だ。二人が焼鳥屋で飲むシーンがある。(小説では、富岡と「男」としか書いてないが、「男」とはたぶん頭取のことだ。)そこでの二人の会話。
頭取「銀行ってところは、出世だとか保身だとか、そんなことを望まなきゃ、それはそれで気楽な場所だ。ところが、どうしても銀行員ってのは、欲を掻く。それがいけない」
富岡「そうですかね。あんまり無欲なのも考えもんでしょう」「ただ、欲にも、身の丈ってものがある。身の丈に合わない欲を掻くから、面倒なことになる。人もそうだし、実は会社だってそうだと思いますね。できもしないことをやろうとするから無理がある。結局、そんな会社は誰も幸せにしない。社業もうまくいかないし、社員だってストレスで参っちまう。全ての会社には、その会社に合った身の丈の欲ってのがあるんですよ」
頭取「耳が痛いな」「私は、身の丈に合わないことを望んでるんだろうか」
富岡「まあ、そうとも言いきれないでしょうが、水は高いところから低いところへしか流れないってことですよ」(pp. 329-330)
ところで小説は、冒頭、牧野治という人物の遺書で始まる。東京中央銀行の前身の一つ、旧・東京第一銀行で頭取を務め、合併後は副頭取となったが合併前の乱脈融資が発覚して自殺する。(1997年、旧・第一勧銀の宮崎元頭取が、総会屋への利益供与事件発覚後自殺したことを思い起こさせるエピソードだ。)小説の終盤で、中野渡頭取は牧野副頭取の自殺をどう捉えるべきか、ずっと考えてきたと、牧野派の筆頭子分であった紀本常務を前に告白する。
「当時の私は、その死をどうとらえていいかわからなかった」「君がいったように、新銀行に迷惑をかけたから亡くなったのか。それとも他に死ななければならない理由があったのか。だが、その死の意味について深く検討する余裕のないまま、我々は損なわれた社会的信用の回復に奔走し、同時に、人心が分裂した行内をいかにまとめていくかという難問に立ち向かわなければならなかった」(p. 355)
・ ・ ・
「牧野副頭取は、事実を隠蔽するために死んだ」「自分の名誉と、そして君たち旧東京第一銀行の行員たちの将来のために、彼は事実を隠蔽することを選んだんだ。はっきりと言おう。牧野副頭取のその選択は、間違っていた。彼は死ぬべきではなく、生きて真実を明らかにし、責任を取るべきだったと思う」(p. 358)
これは半沢のお株を奪うような厳しい言葉だ。最近も似たような事件があっただけにグッと心に迫るものがあった。
フレデリック・フォーサイス『悪魔の選択(上・下)』(角川書店、1979年) [読書]
今年の連休は(大体いつもそうなのだが)、遠出はせず、近くを散歩したり、本を読んだり、DVDを見たりして過ごした。読んだ本の一つが、フレデリック・フォーサイス『悪魔の選択』だ。フォーサイスは私が大学生から20代のころ(1970年代終わりから80年代)にかけて結構流行っていた。私もこの本や『ジャッカルの日』、『オデッサ・ファイル』を読んだ記憶がある。今回、そんな古い本を読み返すきっかけになったのは、混迷を続けるウクライナ情勢だ。確か、あの本もウクライナ問題を取り上げていたな、と。この本の訳者あとがきは、この作品は30年後にも読まれるだろうかとの質問に対し、フォーサイスが「おそらく読まれないでしょう」と答えたことを記しているが、そんなことはない。現に私は30年後に読み返したわけだから(笑)。
ストーリーは、ソ連の食糧危機、クレムリン内部の権力闘争、米ソ対立、その狭間にあるヨーロッパも含めた諜報合戦、ウクライナとユダヤ人の民族問題などが複雑に絡まりながら展開する。中心人物の一人は、アンドルー・ドレークというイギリス人だが、彼はウクライナからの亡命者の息子という出自を持つ。フォーサイスはウクライナの状況を簡潔かつ的確に描く。
「かつての帝政ロシアがそうであったように、革命後のソビエト帝国も、外部から見るかぎり一枚岩の強固さを保っているが、じつはふたつのアキレス腱を内にかかえている。ひとつは2億5千万の人民にめしを食わせるという難問である。もうひとつは、いうところの“民族問題”である。ロシア共和国の支配する14の共和国の中には、数十の非ロシア民族がいるのだが、そのうち最も人数が多くて、おそらく最も民族意識が強いのは、ウクライナ人である。」「ウクライナはその昔から、それが没落の原因となったのであるが、東西ふたつに分裂していた。西ウクライナはキエフからポーランド国境に至る地域で、残る東の部分は、数世紀にわたってロシア皇帝の支配下にあったため、西よりもロシア化の度合いが進んでいる。西は、ほぼ同じ期間、旧オーストリア・ハンガリー帝国の一部だったのである。・・・ウクライナ人のあいだに見られる西ヨーロッパ的なものの残滓は、読み書きひとつとっても明白で、たとえば彼らはローマ字を使い、シリル字母は用いない。また、宗教でいえば、彼らの圧倒的多数は東方帰一教会の信徒であって、ロシア正教には属していない。」(上巻、pp. 17-18)
あることがきっかけで、ドレークはウクライナ内で反クレムリン活動を行うユダヤ人たちを仲間にし、彼らはKGB議長の暗殺に成功する。そのユダヤ系ウクライナ人はイスラエルに亡命し、世界にことの顛末を公表する計画だったが、ウクライナ脱出のハイジャックに失敗し、西ドイツに拘束されてしまう。そこで、第二の手段としてスウェーデンの大型タンカーを北海でシージャックし、ハイジャック犯のイスラエルへの移送を要求する。これを物語の縦糸とすれば、横糸は大国間のパワーゲームだ。この時期、ソ連ではかつてない食糧危機が進行しつつあった。アメリカやイギリスはその情報をかなり正確に把握していたが、問題はそれにどう対応すべきかだった。クレムリン内部では対欧米主戦論を主張するグループが、現書記長の「失政」をネタに権力闘争を仕掛け始めており、ソ連をあまり追い詰めるのも危険だったのだ。諜報合戦で大活躍するのが、イギリスの秘密情報部に所属するアダム・マンローだ。ロシア人並みにロシア語を駆使する彼は組織に対してある秘密を持っていた。彼のかつての恋人がロシア人で、何とクレムリン内部で働いていたのだ。ドレークと並ぶ、この物語のもう一人の主人公はマンローと言ってよいだろう。
フォーサイスの魅力のひとつは緻密に組み立てられた筋立てだが、ところどころにさりげなく書き込まれた寸評も魅力的だ。例えば、30年前に読んだとき以来、(詳細はともかく、その主旨が)ずっと記憶に残ったのはつぎの一節だ。
「人間世界の営みには数限りない分野があり、どんなに狭く、怪しげな分野にも、それぞれその道の専門家がおり、信奉者がついているものである。そしてその連中は、集まってしゃべり、議論し、情報を交換し、最新のゴシップを分かちあう場所を必ず一か所くらい持っている。東地中海における船舶の動きは博士論文のテーマにこそなりにくいが、この地域で失業中の船員-アンドルー・ドレークはその一人に化けていた-にとっては大いに興味をそそられる話題である。こうした船の動きについては、ピレエフス港のヨットハーバーの前にある、カボドーロという小さなホテルが、その情報センターになっていた。」(上巻、p. 178)
その後、インターネットの発達によって、「数限りない分野」の情報が全世界的な規模でウェブ上に共有されるようになったが、まだウェブ化されていない(あるいは、決してされることない)貴重な情報が一方で無限にあるに違いない、と思ったりする。この本が出版されたあとの展開ということで言えば、1991年12月25日のソ連崩壊がある。本書の英語版原著の出版が1979年だったことを考えると、つぎのセリフはけだし卓見と言うべきだろう。
「いつか、あまり遠くない将来、ロシア帝国は瓦解しはじめるだろう。いずれ近いうちに、ルーマニア人が愛国心を発揮するだろう。ポーランド人やチェコ人も。つづいてドイツ人やハンガリー人が、バルト人やウクライナ人が、グルジア人やアルメニア人が-ロシア帝国は、ローマ帝国や英帝国と同じように、ひび割れ、崩れ去るのだ。支配者たちの傲慢さが奴隷たちの忍耐の限度を越えるのだ。」(下巻、p. 205)
ドレークが、乗っ取ったタンカーの船長に語った言葉だ。セリフの半分以上は当たっているが、歴史はなかなか単純に単線的には進まない。それは、「傲慢さ」と「忍耐の限度」の間にかなり大きな幅があるせいかもしれない。
原田節雄『ソニー 失われた20年』(さくら舎、2012年) [読書]
前々回の記事で辻野晃一郎『グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた』(新潮社、2010年)を取り上げたが、ソニー本としては、もう1冊、原田節雄『ソニー 失われた20年』(さくら舎、2012年)を外すことはできない。やはりソニーの元インサイダーによる経営批判の書であり、歴史的、制度的な情報が詳しいことに加え、これまでの多くの経営幹部を個人名で批判のまな板にのせている。個人名を挙げて批判するのは、「悪いのは組織ではなく個人である」との著者の考えによる。
著者によれば、大賀は優秀なライバルたちを排除して後継者を育てず、出井は自己顕示欲の強いアメリカかぶれ、ストリンガーに至ってはそもそもソニーの事業をまともに把握していなかった、ということになる。辻野氏に関しても、批判的に紹介している(p. 305とp.329の2箇所)。全くの部外者である私が、こうした個人批判の妥当性を適切に評価することはできないが、企業経営の最高責任者が長期にわたる業績低迷の責任を負うべきことは当然であろう。
ただ、私にとって最も興味深かったのは、主に出井時代に行われた組織改革、人事制度改革に対する著者の評価だ。1990年代後半から2000年代前半にかけて、日本の経営者や評論家、メディア等の間では無批判なアメリカ模倣がある種の流行となったが、そうした動きにかなりの違和感を抱いていた私にとって、「やっぱり」という指摘がいくつもあった。以下、いくつか例を挙げる。
* * *
・ 大賀時代に導入された「成果主義」(p. 75)。「間接業務に成果主義が導入されると、成果を文字として文書に残さなければなりません。」「誰かが何かを成し遂げたときには、その周囲に大勢の名もない協力者が存在します。ところが、大賀以降のソニー流成果主義の下では、あたかも自分一人が音頭を取って成功したとしなければ評価されません。当然のごとく、自分が成功させたと宣伝する社員が増えてしまいます。」
・ 1994年、社内カンパニー制の導入(pp. 138-146)。「従来から馴染んできた事業部制を廃止し、テレビ、オーディオ、ビデオなどの分野の事業部門を名目上、分社化したのです。」「事業部制に比べたカンパニー制とは、各ビジネスユニットへより大幅に経営権限を委譲した事業形態で、部門ごとに販売や開発の責任を持たせるだけではなくて、擬似的に投資や資金調達の責任まで持たせる形態です。各カンパニーにプレジデント(いわゆる社長ではない)を置き、それなりの責任を与えて独自に業績を上げてもらおうという考え方のカンパニー制ですが、それはカンパニー制への改名や改革を必要とするものではありません。それは事業本部と営業本部を再編成すれば済むことです。」(各カンパニープレジデントは)「出井に気に入られるために、自分が取り仕切るカンパニーの収益だけを考えるようになります。そうして、カンパニーの機能を統合的に管理する経営ではなくて、各カンパニーの収益を単純に合計する経営が進められていきます。」「ソニーが市場で勝負する商品を決めたり市場から撤退する分野を決めたりする企業戦略は、一つの傘の下で立てられるべきもので、個々のカンパニーのアウトプットから判断するべきものではありません。」「単一分野の事業を各カンパニーに分割して丸投げしていては、経営資源の活用などできませんし、全体最適を考えることもできません。また、事業部門どうしのシナジー効果が強く期待されるソニーのような企業では、単純に不採算部門から撤退してもいけません。」
・ 事業部門別成果主義(EVA)(pp. 156-164)。「ソニーのEVAとは、事業部門別成果主義のことで、同一企業の中で偶然、割り振られた担当事業の部門ごとに報酬格差を付けることです。」「心ある事業部長なら、短期と長期の事業をバランスよく計画して業務を進めます。もちろん、自分の事業部だけの業績を考えて働くこともありません。それでもソニー全体のことを考える役員が上に一人もいなければ、そして自分のことだけしか考えない役員ばかりになったなら、ソニーの全体最適や時間最適を考える部長の数も減っていきます。」「ソニーのEVAのさらなる問題は、その業績配分が個々の社員にとって個人別の配分比率なのか、人員構成を無視した部門別の総額配分比率なのか、まったくわからないことです。実際は、所属する社員の格付に応じた、個人業績給の配分割合比率になります。」「EVAは企業評価尺度の一つであるとしても、会社内の部門評価尺度として使える評価システムではありません。EVAはソニー株式会社本体を同業他社と比較するときだけに適用できる単純な評価尺度です。」
・ C3チャレンジと個人成果主義(VB/CG)(pp. 164-186)。2000年に導入されたC3(Cキューブ)チャレンジ制度とは、「約束(commitment)をベースにして、会社(安藤社長)と個人(社員)の間に新しい関係を構築し、真の貢献・成果(contribution)を期待し、それにふさわしい報酬(compensation)の実現を目的とする制度です。」「C3チャレンジでは、C3チャレンジシートを記入して、個人が半期ごとに自分の仕事の現状と進捗を確認し、上司と話し合って業績評価を決めて、報酬の根拠にしていきます。」「ほとんどの昇格は恣意的に決まりますから、この半期ごとの評価は業績給へ反映されるものだと捉えるべきでしょう。実際、C3チャレンジシートの上司評価が何年も連続してAクラスでも、いつまでも昇格しない人もいます。」
「目標設定による成果主義、C3チャレンジ制度の導入にともない、バリューバンド(value band)という職能格制度が社内に導入されました。職務遂行能力で判断する職能資格制度の給与体系を廃し、職務を通じた貢献に着目して、その価値を評価・判定し、会社と個人の関係をより対等にするのが目的だとされています。」「バリューバンド制度は、上司が部下に異動を言い渡すことで、簡単に年俸を上げたり下げたりすることができるツールになるのです。」「サラリーマン社会では、社員個人が担当する職務は、個人が自分勝手に決められるものではありません。それは上司が決めるものです。」「上司の目が節穴だとしたら、そして上司が私利私欲の人だとしたら、その部下は悲惨です。」
・ 1997年、取締役会の改革と執行役員制度の導入。2003年、委員会等設置会社への移行(pp. 196-207)。「ソニーは井深社長の時代、1970年に社外取締役制度を導入しています。・・・ニューヨーク証券取引所(NYSE)へ米国委託証券(ADR)の上場を始めたことでNYSEの上場規則が適用され、2名の社外取締役を登用せざるを得なかったのです。」「ソニーは1997年に38人の取締役を10人に絞り込み、そのうち3人を社外取締役にしました。商法上の取締役から外れた人の多くは、実際の業務遂行に責任をもつ執行役員になり、執行役員専務、執行役員上席常務、執行役員常務の肩書きが与えられました。」「取締役と執行役員の分離は、経営を監視する前者と日常業務を担う後者を分けるためだとされます。・・・しかし、まったくバカげた話です。企業戦略が立てられない社外取締役に、その企業の経営監督はできないからです。」「複雑な業態の大企業で社外取締役が関与できることは皆無に近いでしょう。」「取締役から社内の人間を排除していくことが目的です。すなわち、ソニーでは政治の世界から技術者を排除することになります。」「社外取締役は該当企業の事業運営の門外漢ですから、会議で必要とされる議論には参加しないで、自分の得意分野のことを延々と話し続けます。」
「ソニー凋落の起点だと筆者が確信する2003年の委員会等設置会社移行時の取締役会と取締役の構成を表21に・・・示します。」それによると、全取締役17人中、8人が社外取締役。「ソニーの社外取締役に聞きたいことがあります。あなたたちは、ソニー本社の何を知り、ソニー関連会社の何を知り、ソニーのロゴの歴史と意味をどれだけ理解しているのかと。そして、派遣社員や末端の従業員を含めて、ソニーの名の下で働く人たちとソニーという会社をどれだけ大切にしているのかと。」「出井時代から、ソニーの社外取締役制度とは、ソニーのことを知らない社外の有名人を集めて、仲良しグループの互助会を構成する仕組みのことになりました。」
* * *
それぞれの制度のネガティブな側面を強調しすぎた引用になっているかもしれない。しかし、これらの新たに導入されたアメリカ流の(?)制度が運用の仕方によっては企業経営に大きな負の影響をもたらすことは、いくら強調してもしすぎることはないだろう。
このほか、本書では、ソニー、パナソニックが推すブルーレイディスクと東芝が推すHDD DVDの規格争い、非接触ICカードの規格争い(ソニーが開発したタイプCはJR東日本のスイカに使われたが、日本の官公庁の多くはモトローラが開発したタイプBを使っている)などに関する記述が興味深かった(第8章)。こうした規格争いは、単に業界内の技術競争ではなく、他業種との連携や国際政治が絡んだ覇権争いになっているのである。官をたたいて、その役割をただ低めればよいかのごとき最近の風潮が、いかに皮相なものか思い知らされる。
ソニーの経営不振は一企業の問題にとどまらず、日本経済・社会のあり方をどう考えるかという大きな問題とダブっている、との感を強く抱いた。
辻野晃一郎『グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた』(新潮社、2010年) [読書]
ウォルター・アイザックソンの『スティーブ・ジョブズI・II』(講談社、2011年)を読んで思ったのは、日本の電機メーカーはどうしてダメになってしまったのか、という問いだ。そのヒントを得るべく、この春、数冊の「ソニー本」を読んでみた。ここに取り上げる辻野氏の本は、製品開発のマネジャーとして最前線にいた著者の実体験を描いたものだ。
彼は、1957年生まれ(私と同年齢だ!)、慶応の工学研究科を出てソニーに入社したエンジニアで、会社派遣でカリフォルニア工科大学にも留学したエリートだ。その後、デスクトップパソコン「VAIO」の黒字転換、テレビのチャンネル・サーバー「コクーン」の開発、DVDレコーダー「スゴ録」の大ヒットなどで重要な役割を果たす。
しかし、スゴ録の大成功に対し、あるトップマネジメントは評価するどころか、「まあ、ソニーだからなぁ。出せば売れるんだよ」と言い放ったという(p. 149)。さらに、社内では別のカンパニーで、別のDVDレコーダー(ソニー・コンピュータエンタテインメントのPSX)の開発が始められており、スゴ録の大成功にも関わらず、PSX側のカンパニーに吸収統合され、辻野氏はお役御免となってしまう。
彼のソニーでの最後の仕事となったのは、iPodに打ち勝つべき新たなウォークマンの開発だった。重要な証言なので、少し長くなるが、以下に抜粋、紹介する(本書、第7章「ウォークマンがiPodに負けた日」より)。
* * *
・ (iPodとiTunesを商品化し)アップルは徐々にパーソナルオーディオの市場を席巻し始めた。本来、この脅威に対抗すべきは、ソニーのウォークマン部隊であったが、彼らの危機意識は低く、動きは悪かった。勝者の驕りというか長いことウォークマンのポジションは盤石で、ウォークマンが駆逐される時が来るなどということを誰も想定すらしていなかったのであろう。
・ 危機意識を強めたソニーがようやく重い腰を上げたのは、2004年の年末のことであった。それまでの、ハードウェア側と音楽コンテンツ側のばらばらの動きを改めようと、日本のハードウェア部隊と、米国の音楽コンテンツ部隊を統合した「コネクトカンパニー」が設立されたのである。
・ (私に)突如、このコネクトカンパニーをやって欲しいという声がかかった。しかし、それを最初ははっきりと断ったことも既に述べた。・・・唯一可能性があるとすれば、ソニー本体とは別の新会社を起こしてチャレンジする以外にないと思い、その考えに沿った提言をまとめたのだ*。会社からは、年が明けたら私が提言した方向で進めるという返答があり、最終的にはコネクトカンパニーを引き受けることに決めた。
* 提言には、「ソニー本体とは別の会社にして、ソニーの出資が50%未満の新会社を作ってチャレンジする」ことが含まれていた(p. 23)。
・ しかし、コネクトカンパニーの立ち上げは最初から難航した。ウォークマンはパーソナルオーディオ・カンパニー(PAC)の管轄になっていたが、コネクトカンパニーはPACとは別に作られたので、まず、ウォークマンの主力部隊を大至急コネクトカンパニーに移さねばならなかった。
・ 本来であれば、カンパニー発足時にPACをコネクトカンパニーに統合するような組織変更や人事をトップダウンで断行しておくべきであるのに、PACを残したままコネクトカンパニーが設立され、組織の立ち上げは当事者同士の調整に委ねられてしまったのだ。年明けの設立の話もいつの間にかうやむやになった。
・ 当然のことながら、コネクトカンパニーはPACから敵対視され、リソースの統廃合にはあの手この手で抵抗されて四苦八苦した。
・ コネクトカンパニーの本質は、ソニーのエレクトロニクスビジネス側のハードウェアチームと、エンターテインメントビジネス側のコンテンツチームを密結合させて、ネットワーク時代に合わせた一気通貫の新たな生態系(エコシステム)を構築することにあった。エレキは日本中心、コンテンツは米国中心に動いていたので、この統合は、日米にまたがったリソースの統合でもあった。そのため、私はハードウェアを主に担当する立場、ということになり、もう一人、コンテンツを主に担当するフィル・ワイザーというアメリカ人のプレジデントが任命された。・・・ コネクトカンパニーは、私と彼の二人のコ・プレジデントの共同責任体制、ということになったのである。
・ 二人のプレジデントによる共同経営といういびつな布陣が、コネクトカンパニーの意志決定を複雑なものにしたことは間違いないが、それは、今や、エレクトロニクス産業とエンターテインメント・コンテンツ産業の両方のビジネスを保有し、それらをグローバルに展開するソニーという会社の宿命でもあり、その複雑系を象徴する布陣でもあった。
・ 日に日に勢力を伸ばすアップルを追撃するためには年末商戦を逃すわけにはいかなかった。9月(2005年)に、半ば見切り発車で新商品発表会を行い、アップル追撃の切り札としてウォークマンAシリーズとコネクトプレーヤーによるソニーウォークマンの新しい生態系をアピールした。
・ しかし、そうした我々をあざ笑うかのように、アップルは同じ日に彼らの次の戦略商品であったiPod nanoの発表をぶつけてきた。新商品発表会でスピーチをする直前、スタッフが入手してきたiPod nanoが手元に届いた。彼らの新製品を一目見た瞬間に、私は敗北を悟った。
・ 予想されていたこととはいえ、発売後のコネクトプレーヤーに対する評判は散々なものであった。新しい執行部は、なぜか最初からコネクトカンパニーに対して厳しかったが*、これによって遂にコネクトカンパニーは設立後わずか1年余り、ようやく最初の商品を世に出した直後に、全面見直し、という事態となり、実質解体されて、もともとのパーソナルオーディオ部門の中に再度組み込まれることとなった。
* 2005年9月、「ウォークマンAシリーズ」の試作機を担当副社長に見せに行ったところ、「そもそもお前はなんでこんなものを作ってるんだ? 余計なことはやめてアップルに行ってiTunesを使わせてくれと言って頭を下げれば済む話だろ」と言われたという。著者が「あなたにはプライドというものはないんですか?」と問い返すと、副社長の返事は、「プライド? お前、プライドでいくら儲かると思ってるんだ?」だった(p. 24)。
・ ソニーのガバナンスが混乱する中で生まれたコネクトカンパニーは、最初から短命を運命づけられていたのかもしれないが、こうして継続性を断たれ、その構想を具体化していくことも、失敗から学んでその経験を次の展開に生かすことも、出来なくなった。
・ 従来のやり方では勝負できない時代になったからこそ、本社直轄でコネクトカンパニーが作られたはずであったが、それは再び、従来のやり方の中に戻されていった。
・ コクーンで道を断たれ、再びコネクトで道を断たれた自分にとって、これ以上ソニーに残る理由は、もはやどこにも見当たらなかった。
* * *
カンパニー同士の協力関係の欠如、それらを調整、統合すべきトップマネジメントの不在、無責任がひしひしと伝わってくる。これじゃあ、ダメだ。ソニーがダメになったのは従業員の無能ではない。事業戦略や組織デザインの失敗とトップマネジメントの無能、無責任ではないか、そんな思いに強く駆られる。著者のソニー経営陣に対する批判は(実名で記した相手に関しては)遠慮がちに思われるが、それでも、ところどころ(実名を伏せた相手に関しては)強い無念や激しい怒りが伝わってくる。
本書の後半にはグーグル日本法人での経験が書かれているが、ソニーでの経験談と比べ、やや表面的、抽象的な記述となっている。事業部門間の関係やトップマネジメントの能力、責任について、ソニーと比較対照するように書かれていれば、より興味深い内容になったと思われる。また、著者は日本人の「完璧主義」がネット時代に出遅れた一因だと言うが(p. 242)、ジョブズのアップルもなかなかの完璧主義だったことを考えると、そうとも言い切れないと思う。
ともあれ、著者はグーグル退職後、新たな会社を起こしたとのこと、陰ながらその成功を祈念したい。
ウォルター・アイザックソン『スティーブ・ジョブズI・II』(講談社、2011年)(2) [読書]
(承前)
・ 1985年9月、ジョブズは自らが創業したアップルを去る。その後しばらく、アップルは高業績を維持するが、1990年代に入ると市場シェアも売り上げも落ち、特に1995年8月に発売されたウィンドウズ95がブームになると急速に売り上げを落とした。CEOは、ジョン・スカリー、マイケル・スピンドラー(1993年)、ギル・アメリオ(1996年)と交代するが、業績は悪化の一途をたどる。ジョブズ再登板の道が徐々に開かれていく。
・ 1997年1月、ジョブズは非公式・非常勤のアドバイザーとしてアップルに復帰する。彼が最初に行ったのは、「でたらめに広がった製品ラインに手をつける」ことだった。アメリオは取締役会の支持を失ってクビを切られ、ジョブズは正式なアドバイザーとなる。さらに9月には、「interim CEO」(暫定CEO)の職に就き、12月には「indefinite CEO」(無期限CEO)となる。
・ ジョブズの経営者としての優れた資質について、ジョブズをして「精神的なパートナー」(第II巻、p. 94)と言わしめたジョニー・アイブは、次のように語っている(第II巻、p. 101)。さりげない一言に聞こえるが、トップマネジメントの判断力の重要性を十分に示している。
「会社というのは、アイデアやすばらしいデザインが途中でどこかに行ってしまうことが多い場所です。私や私のチームがどのようなアイデアを出しても、スティーブがここにいて我々をプッシュし、いっしょに仕事をして、我々のアイデアが製品となるよう、さまざまな抵抗を打ち破ってくれなければ、なんの意味も成果も生まれなかったでしょう。」
・ 1998年、家庭用デスクトップコンピューター、iMacでジョブズは復帰デビューを果たす。5色から選べる透明ボディーの斬新なパソコンだ。(残念ながら、当時の私は食指が動かなかったが。)ジョブズは、経営者として一皮むけたようだった。一つは「集中」(製品ライン、OS機能の絞り込み、製造のアウトソーシング、サプライヤーの絞り込み、製造工程の短縮)。また、社内各部門の「緊密なコラボレーション」と「同時並行のエンジニアリング」。
・ パソコン脇役論も出てくる中、ジョブズは新たに音楽プレイヤー、ビデオレコーダー、カメラに至るさまざまな機器を連携させる「デジタルハブ」構想を進め、2001年以降、iTunes、iPod、iPhone、iPadなどのソフト、ハードを次々に具体化していく。アップルが孤高の「統合アプローチ」を採ってきたことが、ここでプラスに働いた。ただ、それだけではない。ジョブズに構想力だけでなく、実行力もあったことが大きい(音楽業界やアーティストの説得など)。
・ ジョブズは、スタンフォード大学の卒業式でのスピーチ(2005年6月)で、自分の人生における転機として3つの出来事を挙げている。①大学を中退したこと、②アップルを追い出されたこと、そして③ガンになり死を身近に意識したことだ。ジョブズの膵臓ガンは2003年に見つかった。春にiTunesストアが発表された年の秋だ。
* * *
アップルとマイクロソフトの事業戦略の違いでよく取り上げられるのは、クローズドで行くかオープンで行くかだ。ジョブズの死期が近づいたころ、ビル・ゲイツが見舞いに訪れた。そのとき、二人はこの問題についても話している。
ふたりは、仕事人生を通じて、対立する基本原理をデジタル世界に見た。ハードウェアとソフトウェアを一つにまとめるべきかオープンにすべきかという問題だ。
「普及するのはオープンな水平モデルだと思っていた。でも、統合された垂直モデルもすごいのだと君が示してくれた」
ジョブズもお返しをする。
「君のモデルもうまくいったじゃないか」
ふたりとも正しかったのだ。パーソナルコンピュータの時代、どちらのモデルも有効で、さまざまなウィンドウズマシンとマッキントッシュが共存できたし、モバイル機器の時代になってもそれは変わらないだろう。
しかし、二人の話を私に語ってくれたあと、ゲイツは1点、警告をつけ加えた。
「スティーブが舵を握っているあいだは統合アプローチがうまくいきましたが、将来的に勝ち続けられるとはかぎりません」
ジョブズも、最後に、ゲイツに対する警告を付け加えずにはいられなかった。
「もちろん、彼の分断モデルは成功したさ。でも、本当にすごい製品は作れなかった。そういう問題があるんだ。大きな問題だよ。少なくとも長い目で見るとね」
(第II巻、pp. 406-407)。
見舞いに訪れたときの様子を話してくれたゲイツが最後に、統合アプローチも成功するという見解をアップルは示したが、それは「スティーブが舵を握っている」あいだだけだとコメントしたことを伝えると、ジョブズは、そんなばかなことがあるかと笑った。
「そういう形で優れた製品を作ることは誰にでもできる。僕だけじゃない」
では、エンドツーエンドの統合を追求してすごい製品を作った会社はほかにどこがあるのかとたずねてみると、ジョブズは考え込んでしまった。ようやく返ってきた答えは、
「自動車メーカーだな」
だった。しかも、一言、追加される。
「少なくとも昔はそうだった」
(第II巻、pp. 409-410)。
* * *
もう一つ、印象深かったのは、1997年にアップルに復帰して以降、2000年代の成功をもたらしたカギであるジョブズによる「集中」、「統合」だ。
マーケティング的な考え方で各部門に製品ラインを増やしたり、百花繚乱、咲くにまかせたりせず、優先順位の高いもの、ふたつか3つに絞ることをジョブズは求める。これがジョブズの強みだとクック(アップルの現CEO)は指摘する。
「彼以上に周囲のノイズをシャットアウトできる人はいません。だからごく少数のものに集中し、多くのことにノーと言えるのです。それを上手にできる人はめったにいませんよ」
古代ローマでは、凱旋した将軍が通りをパレードする際、「メメント・モリ(死を忘れるなかれ)」とささやきつづける従者がその後ろに付き従っていたという。自分も死ぬ存在だといさめられれば、英雄も物事を正しく判断し、多少は控えめになるというわけだ。
(第II巻、p. 271)。
もっとも、集中する対象を誤ってはいけない。経営がうまくいっていない企業は、事業戦略に関して言えば、ちゃんと集中していないか、間違ったことに集中しているかのいずれかであることが多いと思う。それは基本的には経営者の責任だ。経済環境や従業員のせいにしてはいけない。
ウォルター・アイザックソン『スティーブ・ジョブズI・II』(講談社、2011年)(1) [読書]
2011年10月にスティーブ・ジョブズが死去したのち、ほどなくして出版されたのがこの伝記だ。私もすぐに買い求めたが、上下2巻をちゃんと通読したのは今年の春だった。私がアップルの製品に最初に出会ったのは1985年とかなり古いが、その創業者であるジョブズについては、この本を読むまでほとんど知らなかった。彼は私より2歳年長なのでほとんど同時代人と言ってもいいが、その人生がまるで別世界なのに驚いたし、いろいろと考えさせられることが多かった。
第1巻でカバーされているのは、ジョブズの出生(1955年)から結婚(1991年)までだ。
・ ジョブズの生みの親は、シリア出身のイスラム教徒である父親とドイツ系移民の母親で、二人はともにウィスコンシン大学の大学院生だった。しかし、二人は結婚することがかなわず、ジョブズは生後すぐに養子縁組に出される。養父母になったのは、機械いじりが好きな高校中退の父親ポール・ジョブズとその妻クララだ。生みの母親は「大卒の家庭」を希望したが、それはかなわず、代わりにジョブズを大学まで進学させることを条件に宣誓書にサインした。このことは、ジョブズ自身、のちにスタンフォード大学卒業式でのスピーチの中で語っている(http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html)。なお、ジョブズはその後、生みの母親とは再会するが、生みの父親との再会は固く拒んだ。
・ 中学時代のジョブズは飛び級を経験するなど勉強はできたが、いたずら好きで我の強い子供でもあった。高校時代には、HP社製の部品が必要だからと、CEOに直接電話をかけ、夏休みにHPの工場で働くなど、旺盛な行動力の片鱗も見せる。高校の卒業生で、5歳年長の天才プログラマー、スティーブ・ウォズニアックと知り合ったのもこの頃だ。
・ 大学は、オレゴン州のリード・カレッジに進むが、ここで過ごしたのは1年半だった。必修科目がつまらないと言って中退するのだ。ただ、中退後もしばらく居候して、興味のある授業に出席し、その一つ「カリグラフィー」の授業が、のちに多様なフォントをパソコンで使えるようにしたきっかけとなったのは有名な話だ。また、菜食主義、断食、禅宗、瞑想などにのめり込んでいったのも、この大学時代だ。その後、インドの田舎で7ヵ月間過ごす、といった体験もしている。
・ 1976年、ジョブズとウォズニアックはアップルを設立し、最初の製品であるアップルIを製造販売する。作業場所はジョブズの実家で、作業員は家族や友人だった。1977年に、完全パッケージの一体型パソコン、アップルIIを製造販売し大成功する。
・ アップルの名声を不動なものにしたのはマッキントッシュだが、このプロジェクトは当初、ジェフ・ラスキンという多才な開発者をリーダーとして細々と続けられていた。「マッキントッシュ」という名前も、ラスキンが好きなリンゴの品種にちなんでいる。しかし、このプロジェクトはやがてジョブズに乗っ取られた。ジョブズは、自分が主導していた別のプロジェクト「リサ」を、社長のマイク・スコットから降ろされて、そのリベンジをしたいと思っていたのだ。結局、リサは1983年に、マッキントッシュは1984年に発売されるが、両者にソフトウェアの互換性はなく、リサは2年も経たずに製造打ち切りとなった。この間、ジョブズの熱心な誘いに応じて、ペプシ・コーラのジョン・スカリーが1983年、アップルの社長に就いた。
・ 当初は相思相愛に見えたジョブズとスカリーだったが、1985年春には、事業戦略や互いの性格、言動などをめぐって、その関係にひびが入りつつあった。そして、ジョブズはスカリー追放のクーデター計画を策動するが、逆にスカリーに機先を制されてしまう。こうして、5月にジョブズは何の権限もない会長職に祭り上げられ、9月にアップルを辞任する。
・ 「アップルから追放されたあとに創設した会社で、ジョブズは、良い意味でも悪い意味でも本能のおもむくままに行動した。束縛する者もなく、自由だった。その結果、華々しい製品を次々と生み出し、そのすべてで大敗を喫する。これこそがジョブズ成長の原動力となった苦い経験である。その後の第3幕における壮麗な成功をもたらしたのは、第1幕におけるアップルからの追放ではなく、第2幕におけるきらめくような失敗の数々なのだ」(第I巻、p. 342)。
* * *
私がアップルの製品に出会ったのはちょうどこの頃だった。1985年の秋、私はアメリカ東部のある大学院に留学した。当時、学内のコンピューター・ルームには「Macintosh 512K」や「Macintosh Plus」が入っていた。私が属していた学部では、コンピューター・ルームの受付の右側がMacintosh部屋、左側がIBM PC部屋だったが、Macintosh部屋は満員で順番待ちだったのに、IBM部屋はガラガラだった。Macintosh部屋がいつも混んでいた理由の一つは、当時、その学部で統計学を教えていた先生がマック用の統計ソフトを開発し、それを授業や宿題に使っていたためだが、ふつうのワープロとしてもよく使われていた。いちいちコマンドを打ち込む必要がなく、直感的に操作できるGUI(Graphical User Interface)は、実に革新的で、レポートや修士論文の作成に大いに役立った。
そんなわけで、私が最初に買ったパソコンは「Macintosh SE」だ。日本で買ったら60万円以上はしたと思うが、アメリカの大学で学割で購入したので、20~30万円だったと記憶している。さらに、のちに博士課程に再入学した際には、「Macintosh IIsi」を購入した。ワープロ、表計算ソフトが主な用途で、統計計算は、大学の大型コンピューターで行っていたが、電話回線を介して自宅の端末として重宝した。
しかし、1993年にハワイの研究所に就職すると、そこはIBM PCオンリーの職場環境で、コンパックのPCを買い与えられた。その頃にはWindowsもかなり使いやすくなっていたこと、統計ソフトもMac用より充実していたことなどもあって、急速にMac離れが進んだ。ハワイ時代にノート版のMacである「Macintosh PowerBook」を買ったが、画面が暗く、あまり使わなかった。その後、今年になって「MacBook Air」を買うまでの20年近くの間、Macのパソコンを買いたいと思ったことは全くなかった。
この間も、それ以前も、アップルの経営者の交代や社内のさまざまな闘争に関してほとんど興味、関心がなく、無知だったが、私がアップルの製品を愛用したり、しなくなったりしたのは、(タイムラグや感度の鈍さはあるが)基本的には製品の質、魅力だったと思う。その意味で、本書の中でジョブズが次のように言っているのは、合点がいく。
アップルに来るまで、スカリーは炭酸飲料やスナック菓子など、レシピを気にもしていないものを売る仕事をしており、製品に強い思い入れを持つタイプではなかった。これは、ジョブズにとってこれ以上はないという大罪だった。「エンジニアリングの機微を教えようとはしたんだけど、製品がどのように作られるのか彼は理解できず、最後はいつも口論になってしまった。でも、僕は自分の見方が正しいとわかっていた。製品がすべてなんだ」(第I巻、p. 307)。
それにしても、ジョブズというのはこんなに大変な人だとは知らなかった。世間的なルールを無視しても構わないという信念、人は「賢人」か「バカ野郎」しかおらず、仕事の出来は「最高」か「最低最悪」しかないという極論、ともに歩んできた人間にも感傷を抱かない冷酷な神経、何でも自分の思い通りにしないと気が済まない我の強さ、・・・。ジョブズの下で働くなど、私にはとうてい無理だと思うが、一消費者の立場で言えば、良いものを作って、リーズナブルな価格で売ってくれればそれでよい。経営者にとって最も重要な資質は何か、われわれに問い詰めているようである。
吉田修一『横道世之介』(文春文庫) [読書]
先月、吉田修一の小説『横道世之介』を読んだ。映画も観た。いずれも好感の持てる青春ものだ。舞台がH大学なのも良い。(小説では固有名詞は出てこないが、H大学であることは容易に推測できる。映画ではH大学の建物や標示、掲示などが出ていた。)これまで、大学生を取り上げた小説、映画の舞台というとW大学が目立っていたが(『青春の門』、『ノルウェイの森』など)、こうした多様化は良いことだ。
小説は、横道世之介(よこみちよのすけ)という一風変わった名前の若者が、H大学入学のため長崎から上京して過ごした最初の1年間を、ひと月につき一章、全12章で描いたものだ。入居したアパートで、入学式で、サークルで、教室で、・・・と知り合いの輪は広がるが、親しくつき合うのは何人かに限られる。入学式で隣り合わせた倉持一平(いっぺい)、同じクラスの阿久津唯(ゆい)、彼らとともに入会したサンバ同好会の代表、石田健次、同郷でマスコミ研究会の小沢、授業で一緒になった加藤などだ。加藤と一緒に通った自動車運転教習所では、世之介のガールフレンドとなる与謝野祥子と知り合う。
狭いと言えば狭いが、長崎の高校時代に比べれば随分と人間関係の範囲は広がっている。特に地方にはあまりいないタイプの「人種」がいる。お金持ちのお嬢様、与謝野祥子は地方の田舎にはまずいないタイプだし、同郷の小沢や、地方出身で「高級娼婦」然とした片瀬千春(ちはる)などは、都会で暮らすからこそ存在するタイプだ。
こうした中で世之介は自然体でマイペースだ。女性から見ると「鈍感」らしい。田舎者らしく図々しいところもある。クーラーつきの加藤のアパートに、暑い時期、しょっちゅう泊まり込んだりするあたりだ。一方、とても親切でもある。周囲のほとんど誰に対しても。「できちゃった婚」で阿久津と結婚し、大学を中退した倉持に、頼まれるままにお金を貸したりする。後年の祥子の言によるなら、「立派? ぜ~んぜん。笑っちゃうくらいその反対の人」「ただね、ほんとになんて言えばいいのかなぁ・・・・・・。いろんなことに、『YES』って言ってるような人だった」ということになる。だから、彼の「最期」もそれほど意外ではない。「世之介らしいな」と。
作者の吉田修一は私より11歳若いので、大学生活も10年くらいあと、ちょうどバブルのころだったはずだ(卒業はたぶん1991年ころか)。そのころ私はずっと日本にはいなかったのだが、当時の大学生生活はこんな感じだったのかと、懐かしく思った。サークル活動やバイトは私の時代よりも多様化し、盛んになっている。学生は、ノンポリで、あまりガツガツせず、おとなしい印象だが、これは時代のせいか、H大学生の特徴か、よくわからない。
10年くらい前だったと思うが、H大学を1990年代初めに卒業して、ある大手メーカーの人事マンとして働く青年に出会ったことがある。さまざまな会社の人事担当者が集まった勉強会で話をする機会があったのだが、私は当時流行っていた成果主義的な人事制度改革の動きに対してかなり批判的なことを言った。終わったあと、「実はボクも同じこと思ってるんです」と話しかけてくれたのが彼だった。話は、やがて彼の大学時代のことに移り、過激派学生が少数ながら残っていたH大学では授業や試験が正常に行われず、レポートによる成績評価が多かったこと、彼自身、あまり勉強せずに1年間留年したこと、しかし就職は売り手市場で、企業の採用担当者がキャンパスまで出向き、積極的なリクルーティング活動を行っていたことなどを懐かしそうに話してくれた。世之介と同世代である彼は今ごろどうしているだろうか、とふと思った。
最後に映画について一言。小説の内容を比較的忠実にトレースしていると思う。ただ、小説を読んだときに私が頭の中で勝手にイメージした人物像と映画の中の役者がマッチしないことがあり、(そういう想像をしていた自分自身に対して)笑ってしまった。例えば、主人公、世之介の恋人役である祥子ちゃん、お金持ちのお嬢さんで、しゃべりも天然というか、ちょっとトロい感じだ。私はなぜか、『ふぞろいの林檎たち』(1980年代に流行ったTBSのテレビドラマ)に出てきた柳沢慎吾の女房役、中島唱子(しょうこ)のようなイメージで小説を読んでいた。ところが、映画でこの役を演じたのは吉高由里子、今をときめく若手女優で、なかなかスウィ-トな子だ。これだったら、世之介、もっとガッつかなきゃー(笑)。
村上春樹「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」 [読書]
先週末、村上春樹の新作、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』を読んだ。マスコミ報道がすごく、分量的にもすぐ読めそうだったので、つい衝動買いしてしまった。正直に言えば、私は村上春樹の熱心なファンではない。数年前、文庫本で『ノルウェイの森』を読んだのが最初で、そのあと『羊をめぐる冒険』、『海辺のカフカ』なども読んだが、あまりに現実離れした設定と難解な精神世界の描写について行けず、その後、遠ざかっていた。
したがって、今回の作品をいわゆる「村上ワールド」の中にきちんと位置づけ、評価するなどということは、私にはどだい無理な話だ。しかし、多種多様な読者の一人として気ままな感想を素直に記しておいてもバチは当たるまい。
* * * *
小説の主人公、「多崎つくる」(戸籍上は「作」と書く)は、現在36歳、首都圏の電鉄会社で駅舎の設計・営繕を行うエンジニアだ。彼は名古屋の高校時代、男2人、女2人に彼を加えた5人の親友グループのメンバーだった。彼以外の4人の名字には、赤、青、白、黒という色彩を示す漢字が含まれており、それぞれアカ、アオ、シロ、クロと呼び合っていた。しかし、彼は、大学2年生の夏、他の4人から絶交されてしまう。理由に全く心当たりがない彼は大いに混乱し、半年ほど「ほとんど死ぬことだけを考えて生きていた」。
彼が36になり、ちゃんとしたサラリーマン生活を送っているということは、この辛い時期を何とか生き延びたことを示しているが、生き延びた後の彼は人が変わってしまったようで、高校時代の親友4人のことも封印してしまう。そんなとき、沙羅というガールフレンドが現れ、彼に絶交の理由を探求すべきだと強く勧める。彼女は4人の現在の所在を調べ、つくるは4人を訪ねる「巡礼」を始めた。
* * * *
以下は、私の感想だ。
・ この小説では、名字に含まれる色があちこちで強調されている。赤、青、白、黒という4人の親友の名字もそうだが、このほかに灰、緑も登場する。しかし、これらの色が何を暗示しているのか、私には最後までわからなかった。もっと言えば、色には何の意味もないと思っている。実際、4人のうちの一人、クロは、巡礼に訪れたつくると再会したとき、クロやシロという呼び名を拒否し、ファーストネームであるエリ、ユズと呼ぶように求めた。
「ひとつだけお願いがあるの」とクロは言った。「私のことをもうクロって呼ばないで。呼ぶのならエリって呼んでほしいの。柚木のこともシロって呼ばないで。できれば私たちはもうそういう呼び方をされたくないから」(p. 285)。
小説の途中で登場する「灰」や「灰」の父親の思い出話の中で登場する「緑」も謎めいた存在だ。結局、彼らがこの小説の本筋とどのように関わるのか、私には全くわからなかった。なぜ、村上は読者の注目を色に集めようとしたのか。色に意味がないことを強調するための一種の修辞技法なのか、単に読者の関心をひくためのマーケティング戦略なのか。エリが再会したつくるに対して言ったつぎの言葉は、あまりに当たり前の話ではないだろうか。「王様は裸だ」みたいな。
ねえ、つくる、ひとつだけよく覚えておいて。君は色彩を欠いてなんかいない。そんなのはただの名前に過ぎないんだよ。私たちは確かにそのことでよく君をからかったけど、みんな意味のない冗談だよ。君はどこまでも立派な、カラフルな多崎つくる君だよ。(p. 328)
・ この小説の重要なモチーフはたぶんつぎのようなことだ。これもつくるがエリと再会したシーンの中に出てくる。
そのとき彼はようやくすべてを受け入れることができた。魂のいちばん底の部分で多崎つくるは理解した。人の心と人の心は調和だけで結びついているのではない。それはむしろ傷と傷によって深く結びついているのだ。痛みと痛みによって、脆さと脆さによって繋がっているのだ。悲痛な叫びを含まない静けさはなく、血を地面に流さない赦しはなく、痛切な喪失を通り抜けない受容はない。それが真の調和の根底にあるものなのだ。(p. 307)
確かに、人間関係は楽しく美しいものばかりではない。悲しく醜い面が山のようにある。村上春樹が高く評価されている理由の一つは、おそらく人間のそうした側面を見事に描く力量があるからであろう。私にはとてもできない。そうした側面を知らないからではない。無関心、無意識でもないつもりだ。ただ、深くまともに向き合おうとすれば、自分が傷つき打ちのめされることは必至だからだ。さらに、それを他人に伝えるとなれば、その恥ずかしさ、痛みは想像を絶する。全くアカの他人の話として書くことも無理だ。他人の心の中を見ることは誰もできない。したがって、それを描いたとしても、結局は自分自身の精神世界の投影であるとの疑念はぬぐい去れない。
・ 上のモチーフと深く関連するのは、つくるのガールフレンド、沙羅のつぎの言葉だ。
「記憶をどこかにうまく隠せたとしても、深いところにしっかり沈めたとしても、それがもたらした歴史を消すことはできない」。沙羅は彼の目をまっすぐ見て言った。「それだけは覚えておいた方がいいわ。歴史は消すことも、作りかえることもできないの。それはあなたという存在を殺すのと同じだから」(p. 40)。
これと同趣旨のセリフは、小説の後半部分に至るまで、何度か繰り返し登場するのだが、私はこの箇所を読んで思わずニヤッとしてしまった。というのは、私も全く同じことを考え、このブログに書いたことがあるからだ。
フランス語で「覚えている」、「思い出す」という意味の動詞は«se souvenir (de qn/qc)»だ。名詞としての«souvenir»には、「思い出」、「みやげ」などの意味がある(英語のsouvenirも明らかに同根だ)。語源としては、«sou(s)»「下に」+«venir»「来る」、すなわち「意識の下に来ているもの」、「ちょっとしたきっかけで意識に上るもの」といった感覚だろうか。(2012年3月10日付、当ブログ「モネ「舟遊び」(1887年)、「日傘の女」(1886年)」)
時間の経過は、確かに辛い体験を記憶の奥底に追いやってくれる。そうしないと日々生きていくことはできないからだ。しかし、辛い記憶は単に沈殿しているだけであって、消え去ってしまったわけではない。そして、それは一人の個人の中でのみならず、世代間でも引き継がれていくことがある。(2012年3月18日付、当ブログ「パスカル「パンセ」-時は全てを癒やすか?」)
大作家と同じことを考えたり、書いたりしたというのは、悪い気はしない。私の内なる「つくる(作る)君」もなかなかやるじゃないか、と(笑)。
中島 敦「巡査の居る風景-1923年の一つのスケッチ-」 [読書]
カミュの「最初の人間」を読んで思い出した小説がある。中島敦の「巡査の居る風景-1923年の一つのスケッチ-」だ。中島敦と言えば、「名人伝」、「山月記」、「弟子」、「李陵」など、漢文学の深い素養をもとにしたキレのある短編小説で知られる。彼は33年間という短い人生だったが、中学校教師だった父親の転勤に伴い、11歳から17歳までの6年間、京城(現在のソウル)で暮らしたことがある。「巡査の居る風景」は、その当時の体験をもとにして、20歳の時に書かれたものだ。植民地主義(le colonialisme)というと、政治的、経済的な支配・従属関係で語られがちだが、この小説を読むと、それは人々の精神のありように深く複雑な影響を及ぼすものであることを再認識させられる。
小説は、1923年の京城、朝鮮人巡査の趙教英(ちょう きょうえい)が、街角で見たり、仕事で経験したりしたいくつかの短いエピソードを書き連ねていくというスタイルで書かれている。いくつか紹介しよう。
○ 趙教英は路面電車に乗ると、(巡査という仕事柄)いつも運転手台に立っていた。ある夏の朝、日本人の中学生が電車に乗り、運転手台に入ってきた。運転手が、運転の邪魔になるから客席に移るように言っても従わない。朝鮮人の巡査を客席に移動させないのなら、自分もイヤだ、というのである。運転手が朝鮮人であることを見越した上での態度だった。
○ 電車の中で、座席に座っている日本人の女と、吊革につかまっている朝鮮人の青年が口論している。女は、親切に腰掛けなさい、と言ってやったのに何だと怒る。青年は、女が呼びかけの言葉に使った「ヨボ」(「おい」、「お前」など、主に夫婦間で使われる呼びかけ語だが、日本の植民地時代、侮蔑2人称として、日本人から朝鮮人に対して使われた)が気にくわない。女は、「ヨボ」ではなく、「ヨボさん」と呼んだんだ、と言い返す。女は何が問題なのかわからない。
○ 府会議員選挙の立会演説会で、唯一の朝鮮人候補が演説を始めた。すると、「二十にもならぬ位の汚いなりをした小僧」が、「黙れ、ヨボの癖に」とどなり、警官によって外に引きずり出された。すると、朝鮮人の候補者は、一段と声を上げて次のように叫んだ。「私は今、すこぶる遺憾な言葉を聞きました。しかしながら、私は私達もまた光栄ある日本人であることをあくまで信じているものであります。」
○ 街で日本人の立派な紳士から、非常に丁寧な言葉で、朝鮮総督府のある高官の住居を尋ねられた。その住居を教えると、紳士は丁寧に頭を下げて、教えられた方向に曲がっていった。そのとき、趙教英はある大発見をして愕然とする。「俺は今知らない中に嬉しくなっていはしなかったか。」俺達の民族には「永遠に卑屈なるべき精神」がひそんでいるのかもしれない。
○ 高等普通学校の日本歴史の時間、若い教師が困惑しながら、遠慮がちに征韓の役(文禄・慶長の役)について話した。「こうして、秀吉は朝鮮に攻め入ったのです。」児童たちからは、「まるでどこか、ほかの国の話しででもあるような風に鈍い反響が鸚鵡がえしに響いてくるだけ」だった。
○ 「二十四五の痩形の青年」が、東京から帰ってきた総督を狙撃しようとして、取り押さえられた。「彼の腕を捕えていた趙教英はとてもその目付きに堪えられなかった。その犯人の眼は明らかにものを言っているのだ。」趙教英は自問する。「捕らわれたものは誰だ。捕らえたものは誰だ。」
支配者の傲慢が被支配者の反発や服従をもたらすという単純な図式だけではない。支配者の寛容すらが傲慢と裏腹の関係かもしれず、被支配者の卑屈さや思考停止を招くことも十分あり得るのだ。
趙教英の悩みは深い。
事実彼の気持は近頃「何か忘れ物をした時に人が感じる」あのどことなく落ちつかない状態にあった。果たされない義務の圧迫感がいつも頭のどこかに重苦しく巣くっているといった感じでもあった。しかしその重苦しい圧力がどこから来るかということについては、彼はそれを尋ねようとはしなかった。いや、それが恐かったのだ。自分で自分を目覚ますことが恐ろしいのだ。自分で自分を刺激することが恐かったのだ。
では、なぜ怖いのか。とりあえずは、妻子だ。自分が職を失えば、彼らはどうなるのか。でも恐怖の原因は本当にそれだけなのか? 小説には「・・・・・・・・・・・・」としかない。
カミュ「最初の人間」(Le Premier Homme)(2) [読書]
(承前)
カミュの「最初の人間」の一つの謎は、タイトルの「最初の人間」とは一体何を意味しているのかという点だ。これは、小説の中に何箇所かヒント、ないしは直接的な言及がある。
・ (ジャックの)父親の生活は一生意にそまぬものであった。孤児院から病院まで、当然のように結婚し、彼のまわりに、意思に反して、一つの生活が形成され、それが戦争まで続くと、今度は戦死して、埋葬され、以後は家族にも息子にも決して知られることなく、彼もまた自分の種族の人間の最終的祖国である広大な忘却に飲み込まれてしまった。それは根なし草で始まった人生の到達点であり、ただ当時の図書館の中に子供向きの本として、この国の植民地化について多くの記憶を留めただけであった。(新潮文庫版p. 238)
・ 彼(ジャック)は何年もの間、忘却の土地の暗闇の中を進んできたのだったが、そこでは一人一人が最初の人間であり、父親もなく、彼自身が自分の力だけで成長しなければならなかったし、父親が話相手になる年まで息子の成長を待って、家族の秘密や昔の苦しみや人生経験を語るあの瞬間を、滑稽でおぞましいポロニウスが突然大きくなってラエルテに語りかけるあの瞬間を決して知ることはなかった。(新潮文庫版p. 240)
ジャックの父親、アンリ・コルムリは、アルザスからドイツ人の支配を逃れてやってきた入植者の息子で、ジャックが生まれてまもなく、召集された第1次大戦で戦死する。ジャックの母親は、夫であったジャックの父親についてほとんど語ることがなかった。ジャックは、アルジェの下町の小さなアパートで、母親、母方の祖母、母親の弟(叔父)とともに暮らすが、母親は半ば聾で、叔父も聾者、祖母も含め、一家に読み書きのできる者は誰もいなかったのだ。
こうした環境で育ったジャックが次のような考えを抱くのも自然だった。
・ 彼(ジャック)の中では、地中海は二つの世界に分かれていた。一つは計算された空間の中で、記憶と名前が保存されている世界であり、もう一つは砂嵐が広大な空間の中で、人間の足跡を消してしまう世界であった。(新潮文庫版p. 241)
ジャックが、「父親の転勤によってアルジェに移ってきた本国の若者」を知るようになったのは、リセに通い出してからだ。
・ わずかとはいえ、ジャックは自分は人種が違うという感じを抱いていた。つまり過去もなく、代々続く家もなく、手紙と写真でいっぱいの屋根裏部屋もなく、屋根が雪に覆われる訳のわからぬ祖国の理論上の市民である彼らは、真っ直ぐに照りつけてくる、野性的な太陽の下で成長し、例えば彼らに盗みを禁止したり、母親や女性を守るよう促したりはするが、女性や目上のものに関する数多くの問題・・・(等々)には触れていない、この上なく基礎的な道徳だけを身につけていたからである。(新潮文庫版p. 254)
ジャックも、ジャックの父親も、幼くしてその父親を失い、残された家族や親族から父親について詳しく聞くことなく育てられた。そもそも貧しい入植者として、生きていくことが精一杯の日々の暮らしの中で、過去から引き継ぐべき何ほどの文化、歴史、伝統があったのか疑わしい。自分自身で一から人生を切り拓いていくしかない、そういう意味で「最初の人間」だったのだ。引き継ぐべき過去がないという点では、「根なし草」(déraciné)と言ってもよい。
この小説の全編にわたって漂うのはこうした入植者が抱く「デラシネ感」と貧困であり、それがアルジェリア問題や植民地主義といった問題を相対化、もっとはっきり言えば、希釈化している。少なくとも私の印象は間違いなくそうだ。しかし、よく読むと、それに反するようなこともカミュは書いている。
・ 彼ら(ジャックたち)を孤立させていたのは階級の違いですらなかった。この移民と成り上がりと急速な破産の国では、階級の差は人種の差ほどに顕著ではなかった。子供たちがアラブ人であるときには、彼らの感情はもっと痛ましく、苦々しいものとなった。その上、公立小学校では仲間がいたけれど、リセにまで通うアラブ人は例外的で、彼らは決まって裕福な名士の息子たちであった。(新潮文庫版p. 247)
しかし、このような言及はこの小説ではあくまで例外的だ。小説の最後の方に、アラブ人に対する名状しがたい「恐怖」感を描いた箇所もある。
・ 通りでもし女たちと出会っても、顔を半分覆ったヴェールと白い衣装の上の官能的で穏やかな目だけでは、女たちの様子を窺い知ることはできなかった。また彼らが集まり住んでいる一郭ではたいそう人数が多いので、忍従的で疲れた表情をしていても、その数だけで目に見えない恐怖を漂わせるのであった。その恐怖はときどき夕方一人のフランス人と一人のアラブ人との間で喧嘩が行われるときにも感じられた。喧嘩は同様にフランス人同士やアラブ人同士で行われることもあったが、取り巻きの反応は違っていた。(新潮文庫版p. 335)
・ それは恐らく第一の人生の日常的な現れの下に隠れていたもっと真実味のある生活、第二の人生のようなものであった。それを物語るには一連の暗い欲望と強力だが筆舌に尽くしがたい感覚とが必要であったろう。(新潮文庫版p. 336)
私にとって「最初の人間」の最大の謎は、なぜ、アルジェリア問題がほとんど出てこないのかという点だ。ここで私が「アルジェリア問題」というのは、フランスの植民地主義やアルジェリアの独立運動のことだ。カミュがこの(未完の)小説を遺して死んだのは1960年だが、1954年から既にアルジェリア戦争が始まり、1962年の独立に至ったこの時期、アルジェリアで生まれ育ったノーベル文学賞作家(1957年受賞)が何を言うのか、人々の耳目が集まらなかったはずはない。
一つの可能性は、カミュはこの問題について真っ正面から取り上げるつもりだったが、その急逝によってそれがはたせなかったというものだ。実際、公刊された小説は、「第1部 父親の探索」(RECHERCHE DU PÈRE)、「第2部 息子あるいは最初の人間」(LE FILS OU LE PREMIER HOMME)の2部構成だが、彼が遺したノートによれば、「第1部 遊牧民」(LES NOMADES)、「第2部 最初の人間」(LE PREMIER HOMME)、「第3部 母親」(LA MÈRE)の3部構成となっている。しかも、第3部の中には次の記述がある。
・ 最終部で、ジャックは母に向かって、アラブ人の問題と植民地文化と西欧の運命について説明する。「ああ、そうなの」と彼女は言った。それから包み隠しのない告白と終末。(新潮文庫版p. 381)
しかし、このあとには、つぎのような、いくぶん謎めいた記述もある。
・ この男は神秘をうちに秘めていた。そしてそれは彼が解き明かそうとしている神秘であった。しかし、最終的には、人間たちを名もなく、過去もないものにしている貧困の神秘しかない。(新潮文庫版p. 381)
また、つぎのようにも書いている。
・ 次のようなイマージュで最終部を始めること――何年もの間辛抱強く水汲み水車の周りを、鞭で打たれるのを我慢しながら、またきつい自然や太陽や蠅に耐えながら、ぐるぐる回る盲目のロバ。一見不毛のように思われる単調で、痛ましいその丸い歩みによって、絶えず水がほとばしり出る・・・(新潮文庫版p. 391)
・ 最終部。・・・それから彼は母の方を、次いでみんなの方を見ながら、叫んだ。「土地を返したまえ。貧乏人に、何ももっておらず、あまりにも貧乏なので何かをもとうとか所有しようとは決して望んだことのない人たちに、この国での彼女のように、ほとんどがアラブ人で、何人かはフランス人からなる悲惨な人たちの巨大なグループを構成し、世界で価値のある唯一の名誉、つまり貧者の名誉をもって、執拗に耐えながらここで生活をし、生き延びる人たちに土地を与えたまえ。聖なる者に聖なるものを与えるのと同じように、彼らに土地を与えたまえ。そのとき、私は再び貧乏になって、最悪の追放を受けながら、世界の端で微笑み、満足して死ねるだろう。私の誕生の太陽の下で、やっと私があれほど愛した土地と私が崇めた人たちが、男も女もみな一つになるということを知りながら。」(新潮文庫版pp. 396-397)
こうした記述を見ると、カミュの中では、やはりコルムリ一家のような貧困の中で、過去から何らの遺産を引き継ぐことなく、根なし草として生きていく人々に対する哀惜の情が勝っていると思える。そうした前提で、入植者とアラブ人の対立構造を相対化、希釈化したいのかもしれない。しかし、一方で、両者の間に解消しがたい障壁があることもカミュはよくわかっていたのだ。
カミュは、1957年12月10日、ノーベル賞の受賞晩餐会で次のように述べている。
(全文は、http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1957/camus-speech-f.htmlを参照)
«L’artiste se forge dans cet aller retour perpétual de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s’arracher. C’est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien ; ils s’obligent à comprendre au lieu de juger. »
「芸術家は、自分と他人の間を絶えず行きつ戻りつする中で作り上げられる。それなしでは済ますことができない美しさと、そこから自分を引き離すことができない共同体の狭間で。だから、真の芸術家は、何ごとも軽蔑しない。彼らは裁くのではなく、理解することを自らに課しているのだ。」
これがカミュの真意なら、彼がアルジェリア問題でその政治的立場を安直に表明しなかったのは、「確信犯」だったということになる。
カミュ「最初の人間」(Le Premier Homme)(1) [読書]
アルベール・カミュ(Albert Camus)は、1913年11月17日、アルジェリアのBône(現Annaba)近郊の町、Mondoviに生まれ、1960年1月4日、フランス、パリ近郊フォンテーヌブローの森の南西にある町、Villeblevinで自動車事故のため死亡した。今年はちょうど生誕100年にあたる。交通事故で死んだカミュの鞄の中から、未完成の小説の原稿「最初の人間」が発見されたが、それを公表すべきか否か長らく議論があった。1994年に公刊された今となっても、公表すべきではなかったという人がいる。例えば、私が2009年、パリのフランス語学校で1回だけ授業を受けたことのある女性教師は公表に反対の立場だった。
彼女は、当初、授業担当の予定だった先生が電車のストで来られなくなり、当日の朝になってピンチヒッターを頼まれたのだった。準備の時間がなかったこともあり、なぜかたまたま(?)持っていたカミュの戯曲「誤解」(Le Malentendu)から、5、6ページずつのコピーを2人1組の生徒のグループそれぞれに渡し、それを今から暗記して、宿屋の女主人と娘の会話をみんなの前で再現しなさいと指示した。少々無茶ぶりだったが、今となってはいい思い出だ。それはともかく、彼女は、イントロとしてカミュの簡単な紹介をした際、作家本人が完成した作品とはみなしていないものを公刊するのは反対だと、はっきり言っていた。
当時の私は、そうした彼女の主張の意味を表面的にしか捉えることができなかったが、今回、実際に「最初の人間」を読んでみて、なるほど、これは謎の多い作品だなと思った。例えば、映画版では主要なモチーフとして強調されていたアルジェリア問題だが、小説にはほとんど全く登場しない。逆に言うと、映画版では、小説に全く書かれていないエピソードが挿入されたり、あるいは小説のエピソードが脚色されたりしている。しかも、ほとんどの場合、アルジェリア問題をどぎつく示す方向に変えられている。具体例を挙げよう。
・ 1957年、アルジェ。映画では、作家ジャック・コルムリ(Jacques Cormery)がアルジェに帰郷し、大学でアルジェリア問題について講演する。この話は小説には全く出てこない。
・ 1924年、アルジェ。映画では、少年のジャックがアラブ人の犬の捕獲人の檻を開けて犬を放し、代わりに自分が捕まってしまう。犬の捕獲人の話は小説にも出てくるが、(アラブ人も含め)町の人からは嫌われ者の存在として描かれている(新潮文庫版pp. 174-176、folio版pp. 157-160)。ジャックらは、捕獲人が野良犬に近づこうとすると「ガルーファ(犬の捕獲人のこと)だ、ガルーファだ」と叫んで犬の捕獲を妨害するが、檻を開けて犬を逃がしたりしたわけではない。また、ジャックが犬の捕獲人に捕まったこともないし、そもそもフランス人の悪ガキが貧しいアラブ人の仕事を邪魔するという視点では書かれていない。
・ 1924年、アルジェ。映画では、祖母のお使いで肉を買いに行ったジャックがお金をちょろまかす話が出てくる。小説でも、ジャックがパン屋にポテトグラタンを買いに行ったときの話として、似たエピソードが出てくる(新潮文庫版pp. 112-115、folio版pp. 100-103)。
・ 1924年、アルジェ。映画では、小学校のベルナール先生がジャックの家を訪れ、祖母と母親に対しジャックの進学を説得する。これは小説でも同じ話が出てくる(新潮文庫版pp. 199-201、folio版pp. 179-181)。
・ 1957年、アルジェ。映画では、アルジェに帰郷したジャックがベルナール先生と再会し、アルジェリア問題について小説を書くよう薦められる。ジャックがベルナール先生と再会する話は小説にも出てくるが、先生がジャックにアルジェリア問題を取り上げるように言ったことはない(新潮文庫版pp. 184-185、folio版p. 167)。出てくるのは、例えば次のような話だ。ベルナール先生は自身が従軍し、ジャックの父親も戦死した第1次大戦の話をときどき授業で取り上げ、ドルジュレスの「木の十字架」«Les Croix de bois»を読んで聞かせることがあった。そして、再会したジャックにこの本を渡す。「君は最後の日に泣いていたね。覚えているかね? あの日以来、この本は君のものだ。」«Tu as pleuré le dernier jour, tu te souviens? Depuis ce jour, ce livre t’appartient. »
・ 1924年、アルジェ。映画では、教室でアラブ人のクラスメート、ハムッドがジャックに喧嘩をしかける。小説では、ジャックがアラブ人と争ったというような話は一切出てこない。小学校時代のジャックが喧嘩した話は出てくるが、相手は「ブロンドの髪をした」ミュノだ(新潮文庫版pp. 187-195、folio版pp. 170-176)。喧嘩のきっかけは、ベルナール先生のお気に入りだったジャックのことを、授業中に「お気に入りめが」«chouchou»とささやいたミュノに対し、ジャックが「決闘」を申し込んだことだった。ジャックはミュノをボコボコにし、校長はジャックに立ちんぼのペナルティを与える。この一件は、「勝者」であるジャックにとっても決して後味のよいものではなかった。「そしてかくして知ったのだ。一人の人間に勝つことは相手に負けることと同じくらい苦いものだから、戦争はよくないということを。さらに教育を完全なものにするために、即座に栄光のあとには失墜があるということを知らされた。」«Et il connut ainsi que la guerre n’est pas bonne, puisque vaincre un homme est aussi amer que d’en être vaincu. Pour parfaire encore son éducation, on lui fit connaître sans délai que la roche Tarpéienne est près du Capitole.»
・ 1945年、パリ。映画には出てこないが、小説に出てくるエピソードは、言うまでもなく山のようにある。その中の一つだけを紹介しておこう。
1945年に、兵士の頭巾つき外套姿の年配の国土防衛軍の兵士が、パリの彼の家の呼び鈴を鳴らしたが、それはふたたび従軍したベルナール氏であった。「戦争が起こったからではない」と彼は言った。「ヒトラーに反対なのだ。君も戦ったのだね、ちび君。・・・さてこれからアルジェに帰るんだが、会いに来てくれたまえ。」それ以来ジャックは15年前から、毎年ベルナール氏に会いに行くことになった。毎年、今日のように、暇を告げる前に、戸口で彼の手を握る涙もろいこの老人を抱き締めた。ジャックがもっと大きな発見の方に歩んでいけるように、彼を根なし草にした責任を取りながら、彼を世間に送り出したのはベルナール氏であった。(新潮文庫版p. 196)
・・・lorsqu’en 1945 un territorial âgé en capote de soldat était venu sonner chez lui, à Paris, et c’était M. Bernard qui s’était engagé de nouveau, «pas pour la guerre, disait-il, mais contre Hitler, et toi aussi petit tu t’es battu,・・・, et maintenant je retourne à Alger, viens me voir», et Jacques allait le voir chaque année depuis quinze ans, chaque année comme aujourd’hui où il embrassait avant de partir le vieil homme ému qui lui tenait la main sur le pas de la porte, et c’était lui qui avait jeté Jacques dans le monde, prenant tout seul la responsabilité de le déraciner pour qu’il aille vers de plus grandes découvertes encore. (folio版p. 177)
私は、この文章に出てくるデラシネ(根なし草)-文中では「彼を根なし草にする」と動詞形で使われているが-という言葉は、この小説を理解するキーワードだと思っている。
・ 1957年、アルジェのアラブ人居住区。映画では、ジャックがかつてのクラスメート、ハムッドを訪ね再会する。小説では、そもそもジャックがアラブ人のクラスメートと喧嘩した話はないし、ハムッドもその息子も出てこない。
以上は若干の例示に過ぎないが、私が、「映画版では、小説に全く書かれていないエピソードが挿入されたり、あるいは小説のエピソードが脚色されたりしている」と言う根拠はご理解いただけたものと思う。
<次回に続く>
新美南吉「おじいさんのランプ」 [読書]
東芝の白熱電球製造中止(2010年3月)の広告を眺めながら思い出した童話がある。確か小学校の国語の教科書に載っていた新見南吉の「おじいさんのランプ」(1942年)だ。話のポイントはよく記憶しているが、念のため図書館で借りて再読してみた(『新美南吉童話全集第二巻 おじいさんのランプ』大日本図書、1960年)。
* * *
話の主役は、日露戦争のころ十二、三の少年だった巳之助(みのすけ)だ。彼はまったくのみなし子だったが向上心が強く、人力車引きの仕事で峠を越えて大きな町に行ったとき、「花のように明るいガラスのランプ」があちこちに灯っているのを見て衝撃を受ける。そしてランプ屋の主人に掛け合って、自分の村でランプを売ることと引き替えに、ランプを一つ手に入れる。ランプは最初売れなかったが、ひとたびその利便さが伝わると、巳之助の商売も繁盛し、自分の家を建て、家族も持つようになった。
ところが、やがて隣の町に電気が引かれ、自分の村にもいよいよ引かれることになった。
「以前には文明開化ということをよくいっていた巳之助だったけれど、電燈がランプよりいちだん進んだ文明開化の利器であるということはわからなかった。りこうな人でも、じぶんの職を失うかどうかというようなときには、ものごとの判断が正しくつかなることがあるものだ」(p. 22)。
村会で電気を引くことが決まると、巳之助は誰かを恨まずにはおれなくなり、何と自分がみなし子のときから世話をしてくれた区長さんの家に放火しようとする。しかし、放火のために持ってきた火打ち道具が湿っていて火がつかず、思わず舌打ちする。
「マッチを持ってくりゃよかった。こげな火打ちみてえな古くせえもなァ、いざというとき間にあわねえだなあ」(p. 25)。
この一言で、巳之助は我に返る。
「ランプはもはや古い道具になったのである。電燈というあたらしい、いっそう便利な道具の世の中になったのである。それだけ世の中がひらけたのである。文明開化が進んだのである。巳之助もまた日本のお国の人間なら、日本がこれだけ進んだことを喜んでいいはずなのだ。古いじぶんのしょうばいが失われるからとて、世の中の進むのをじゃましようとしたり、なんのうらみもない人をうらんで火をつけようとしたのは、男としてなんという見苦しいざまであったことか。世の中が進んで、古いしょうばいがいらなくなれば、男らしく、すっぱりそのしょうばいをすてて、世の中のためになるあたらしいしょうばいにかわろうじゃないか」(p. 26)。
巳之助は家に帰って、50くらいあったランプのすべてに石油を注ぎ、村の外れの大きな池に持っていった。そして、一つ一つのランプに火をともしては、岸辺の木にそれらをつるした。
「わしの、しょうばいのやめかたはこれだ」(p. 26)。
そして池の対岸に回り、一番大きなランプめがけて石を投げた。ついで二番目に大きなランプに。三番目に大きなランプを割ったとき、涙が浮かんで、もう狙いを定めることができなかった。
こうして巳之助はランプ屋をやめ、町に出て本屋になった。
* * *
この話は、巳之助おじいさんが、孫の東一(とういち)君に向かって思い出話を語るという形式で書かれている。話し終わったあと、東一君がおじいさんに(ランプを割ったり、捨て去ったりして)「損しちゃったね」と言ったのに対し、巳之助はこう答える。
「わしのやりかたはすこしばかだったが、わしのしょうばいのやめかたは、じぶんでいうのもなんだが、なかなかりっぱだったと思うよ。わしのいいたいのはこうさ、日本が進んで、じぶんの古いしょうばいがお役にたたなくなったら、すっぽりそいつをすてるのだ。いつまでもきたなく古いしょうばいにかじりついていたり、じぶんのしょうばいがはやっていたむかしのほうがよかったといったり、世の中が進んだことをうらんだり、そんな意気地のねえことはけっしてしないということだ」(p. 30)。
この童話に関する私の記憶は、池の周りにたくさんのランプを灯し、石を投げて割るという印象深いシーンで終わっていたが、今回再読して、孫に随分立派なことを語っているんだなと感心した。優れた童話というのは、本来、大人に読み聞かせるべきものなのかもしれない。
1945年8月15日の永井荷風 [読書]
荷風に興味がない方にはどうでもいいことだろうが、1945年の8月15日、永井荷風はどこで何をしていたか。彼の日記、『断腸亭日乗』には次のようにある(以下、引用はすべて『摘録 断腸亭日乗(下)』1987年、岩波文庫より)。
× × ×
八月十五日。陰(くも)りて風涼し。宿屋の朝飯、鶏卵、玉葱味噌汁、はや小魚つけ焼、茄子香の物なり。これも今の世にては八百膳(やおぜん)の料理を食するが如き心地なり。飯後谷崎君の寓舎に至る。鉄道乗車券は谷崎君の手にて既に訳もなく購ひ置かれたるを見る。雑談する中(うち)汽車の時刻迫り来る。再会を約し、送られて共に裏道を歩み停車場に至り、午前十一時二十分発の車に乗る。新見の駅に至る間隧道(すいどう)多し。駅ごとに応召の兵卒と見送人小学校生徒の列をなすを見る。されど車中甚しく雑踏せず。涼風窓より吹入り炎暑来路に比すれば遙に忍びやすし。新見駅にて乗替をなし、出発の際谷崎夫人の贈られし弁当を食す。白米のむすびに昆布佃煮及牛肉を添へたり。欣喜措く能はず。食後うとうとと居眠りする中(うち)山間の小駅幾箇所を過ぎ、早くも西総社(にしそうじゃ)また倉敷の停車場をも後にしたり。農家の庭に夾竹桃の花さき稲田の間に蓮花の開くを見る。午後二時過岡山の駅に安着す。焼跡の町の水道にて顔を洗ひ汗を拭ひ、休み休み三門の寓舎にかへる。S君夫婦、今日正午ラヂオの放送、日米戦争突然停止せし由を公表したりと言ふ。あたかも好し、日暮染物屋の婆、鶏肉葡萄酒を持来る、休戦の祝宴を張り皆々酔うて寝に就きぬ。 [欄外墨書] 正午戦争停止。
× × ×
多少前後関係を説明しないとわかりにくいだろう。1945年の春以降、東京への空襲が激しさを増す中、荷風は東京脱出を試みる。6月2日に、列車の乗車券をようやく手に入れることができ、罹災民専用大阪行きの列車に乗る。明石にいったん逗留した後、岡山に疎開する。もっとも岡山も安全ではなく、6月28日夜の空襲では、「余は旭川の堤を走り鉄橋に近き河原の砂上に伏して九死に一生を得たり」といった経験もした。
荷風が岡山に疎開したのは、当時、友人の谷崎潤一郎が岡山県の勝山町(現在は、岡山県真庭市勝山。中国山地の山の中で、東に津山市、西に新見市がある)に疎開していたという事情もある。荷風は8月に、谷崎に会いにこの勝山に行き、接待を受ける。ただ、長く厄介になるわけにもいかないと、8月15日、勝山から岡山に帰ることにしたのだった。
冒頭に引用した8月15日の項を見ると、食べ物のことばかり書いているのが荷風らしい。終戦に関する記述は最小限だが、その後、次第に様子がわかってくるにつれ、表現も強くなっていく。
・「八月十七日。・・・休戦公表以来門巷寂寞たり。市中の動静殆(ほとんど)窺知りがたし。・・・」
・「八月十八日。食料いよいよ欠乏するが如し。朝おも湯を啜(すす)り昼と夕とには粥に野菜を煮込みたるものを口にするのみ。されど今は空襲警報をきかざる事を以て最大の幸福となす。・・・」
・「八月二十日。・・・とにかく平和ほどよきはなく戦争ほどおそるべきものはなし。」
結局、荷風は8月29日に帰京のための切符を手に入れ、東京へ帰ることとなった。
・「八月廿九日。晴れて風涼し。正午村田氏の細君と共に岡山駅に至り、ツーリストビューローの事務員に面会し、金子(きんす)一包を贈り、東京行二等の切符を手にすることを得たり。事皆意外の成就にて夢に夢みる心地なり。・・・」
別に荷風でなくてもよいが、世代から世代へ歴史を語り継いでいくことは大切だと思う。
宮沢賢治「フランドン農学校の豚」 [読書]
スティーブン・スピルバーグ監督の映画「戦火の馬」は、馬と人間の心の交流を描いた心温まる映画だ。確かに馬は何度も辛い目にあうが、それは人間の側も同じことだ。それに比べ、宮沢賢治「フランドン農学校の豚」における豚と人間の関係はもっと切ないものがある。
この小説は、フランドン農学校に飼われていた食用肉豚の話だ。ある豚が殺される予定の前月になって、国王から「家畜撲殺同意調印法」という布告が出され、家畜を殺す場合、飼い主はその家畜から死亡承諾書を受け取ること、そしてその承諾書に家畜の調印を要することが決められたのだ。このため校長先生は、豚から死亡承諾書をとろうとして苦労する。
× × ×
校長: どうだい。今日は気分がいゝかい。
ブタ: はい、ありがたうございます。
校長: いゝのかい。大へん結構だ。たべ物は美味しいかい。
ブタ: ありがたうございます。大へん結構でございます。
校長: さうかい。それはいゝね、ところで実は今日はお前と、内内相談に来たのだがね、どうだ頭ははっきりかい。
ブタ: はあ。
校長: 実はね、この世界に生きてるものは、みんな死ななけぁいかんのだ。実際もうどんなもんでも死ぬんだよ。人間の中の貴族でも、金持でも、又私のやうな、中産階級でも、それからごくつまらない乞食でもね。
ブタ: はあ、
校長: また人間でない動物でもね、たとへば馬でも、牛でも、鶏でも、なまづでも、バクテリヤでも、みんな死ななけぁいかんのだ。蜉蝣(かげろう)のごときはあしたに生れ、夕(ゆうべ)に死する、たゞ一日の命なのだ。みんな死ななけぁならないのだ。だからお前も私もいつか、きっと死ぬのにきまってる。
ブタ: はあ。
校長: そこで実は相談だがね、私たちの学校では、お前を今日まで養って来た。大したこともなかったが、学校としては出来るだけ、ずゐぶん大事にしたはずだ。お前たちの仲間もあちこちに、ずゐぶんあるし又私も、まあよく知ってゐるのだが、でさう云っちゃ可笑しいが、まあ私の処ぐらゐ、待遇のよい処はない。
ブタ: はあ。
校長: でね、実は相談だがね、お前がもしも少しでも、そんなやうなことが、ありがたいと云ふ気がしたら、ほんの小さなたのみだが承知をしては貰へまいか。
ブタ: はあ。
校長: それはほんの小さなことだ。ここに斯う云ふ紙がある、この紙に斯う書いてある。死亡承諾書、私儀永々御恩顧の次第に有之候儘(これありさうらふまま)、御都合により、何時にても死亡仕るべく候 年月日フランドン畜舎内、ヨークシャイヤ、フランドン農学校長殿 とこれだけのことだがね、 つまりお前はどうせ死ななけぁいかないからその死ぬときはもう潔く、いつでも死にますと斯う云ふことで、一向何でもないことさ。死ななくてもいゝうちは、一向死ぬことも要らないよ。こゝの処へたゞちょっとお前の前肢の爪印を、一つ押しておいて貰ひたい。それだけのことだ。
ブタ: 何時にてもといふことは、今日でもといふことですか。
校長: まあさうだ。けれども今日だなんて、そんなことは決してないよ。
ブタ: でも明日でもといふんでせう。
校長: さあ、明日なんていふやうそんな急でもないだろう。いつでも、いつかといふやうな、ごくあいまいなことなんだ。
ブタ: 死亡をするといふことは私が一人で死ぬのですか。
校長: うん、すっかりさうでもないな。
ブタ: いやです、いやです、そんならいやです。どうしてもいやです。
校長: いやかい、それでは仕方ない。お前もあんまり恩知らずだ。犬猫にさへ劣ったやつだ。
ブタ: どうせ犬猫なんかには、はじめから劣ってゐますよう。わあ。
× × ×
結局、豚は死亡承諾書に爪判(つめばん)を押さされ、殺される。以前、社会人大学院生だったA氏から、この小説とダブらせながら、自らのサラリーマン生活やリストラ体験を綴ったエッセイをもらったことがある。私は、会社、あるいはより広く組織の論理と個人の心情はしばしば一致しないし、個人が組織の理不尽さに憤りを感じることが少なからずあるといったことは全く否定しない。しかし、だからと言って、サラリーマンを「社畜」だと見なすのは、行き過ぎだと思う。
多くの場合、サラリーマン生活は辛いことばかりではない。よい仲間に恵まれ、やりがいのある仕事を経験することも多い。それによって自分も成長する。ちゃんとした組織ならそうしたチャンスは多いはずだ。また、サラリーマンを辞めて自営業(あるいは自由業)を始めたら、全く「自由」になれるというものでもない。自営業の場合、「上司」の指示を受けることはないが、今度は、顧客や取引業者などの意向を気にしなければならない。就業形態と「自由」の関係はそれほど単純ではないと思う。この点は、改めて論じたい。
ジョージ・オーウェル「1984年」 [読書]
K先生は、私が尊敬する同僚の一人だ。頭の回転が恐ろしく速く、博覧強記、それでいてどこか憎めない愛すべきキャラだ。少々口が悪いので「敵」も多い(かもしれない)が、私の場合は、何度か衝突するうちに親しくなっていった。先日も、「福祉」の語源、語義や“welfare”と“well-being”の違いについて(私は、同じ意味という立場だが)、楽しく議論した。K先生は、「福祉」という言葉を初めて日本語として訳出したのは、福沢諭吉だと最初言っていたが、私がそれは違うんじゃないかというと、今度は西周、やがて中村正直ということになった。多少不正確でも、大局を外さないところがK先生らしい。
そんなK先生に、最近メールを送ったところ、文字化けで読めないと返信があった。私はK先生宛のメールは、親愛の情を込めて、いつも「大兄」と書き始めている。そこで、文字化けしても読めるように英文に直して再送した際、それを直訳して“Dear Big Brother,”と書いてしまった。案の定、K先生から皮肉たっぷりの返信があった。曰く、「Big Brotherってのは、オーウエル『1984年』に出てくる、共産党、ってことですよ(私の主要敵の)。ま、読めました。」
実を言うと、私は昨年、オーウェルの『1984年』をかなり丁寧に再読したばかりだ。以前は、何となくプライバシーのない情報管理社会、監視社会の怖さを描いた小説のように思っていたが、それだけでなく、人間が人間を信じられない社会の怖さを再認識させられた。
「ビッグ・ブラザー」というのは、この国(「オセアニア」)の支配者がそう呼ばれているのだが、誰もそれが実際にどんな人物なのかよく知らない。ヒトラーやスターリン、「金王朝」のような目に見える独裁者ではないのだ。ビッグ・ブラザーには、エマニュエル・ゴールドスタインという「人民の敵」がおり、「二分間憎悪」というプロパガンダ・プログラムで毎日のようにやり玉に挙げている。敵を作ることが権力の維持・強化に必須だというのは、古今東西を問わず政治の定石なのだろう。
小説の主人公、ウィンストン・スミスは真理省に勤める役人だが、ビッグ・ブラザーへの違和感を抱えている。そんな自分の本心を同僚や隣人に気づかれないかと恐れる。相手は、油断ならないように見えて、実は同じ考えを共有している同志なのかもしれないし、自分に同情的なように見えて、実はビッグ・ブラザー側のスパイなのかもしれない。全体主義の最も恐るべき本質は、おそらくこの人間不信の連鎖にある。
この小説には「二重思考」(doublethink)という言葉がキー・コンセプトの一つとしてよく登場する。「二重思考とは、ふたつの相矛盾する信念を心に同時に抱き、その両方を受け入れる能力をいう」(ハヤカワepi文庫版、p. 328)。ビッグ・ブラザーやその取り巻きに二重思考が要請される理由は単純だ。彼らは全能で誤りを犯さないことになっている。しかし、実際には全能でも誤りを犯さないわけでもない。このため、「事実の処理に於いて、たゆまない臨機応変の柔軟性が必要となる」のである(p. 325)。
人間不信に二重思考が加わると、コミュニケーションというものは、全くの機能不全になる。例えば、ある人が誰かに「好きだ」と言ったとしよう。しかし、相手は自分の敵かもしれないし味方かもしれない。相手がこれをどのように解釈するか全くわからない。「好きだ」は容易に「嫌いだ」という意味に変換される。実際、この国でよく聞かれるスローガンは、「戦争は平和なり 自由は隷従なり 無知は力なり」だ。
ところで、この「二重思考」と、パスカルの「パンセ」にある「両極端の中間を満たすこと」(2012年5月19日付け当ブログ)の関係をどう整理するか、結構厄介だ。英語でよく使われる表現に“double standard”(二重基準)がある。手許のWebster’s New World Dictionary (Third College Edition)によれば、“a system, code, criterion, etc. applied unequally; specifically, a code of behaviour that is stricter for women than for men, especially in matters of sex. ”とある。男女の性行為に対する評価が例に挙げられているが、実際にはより広い文脈で使われ、差別意識などネガティヴな含意を伴うことが多い。つまり、複数の判断基準を使用者が自分に都合良く使い分けるという意味だ。『1984年』の「二重思考」も、ビッグ・ブラザーに体現される体制の権力維持、永続化が目的であるところが問題だ。
つまり、複数の基準や原理を柔軟に使い分けること自体が問題ではなく、目的の道徳性、正当性が問われていると私は思うのだが、では、誰がいかにして目的の道徳性なり正当性を証明するのかと問われれば、残念ながら自分自身納得のいく答えはまだない。
宮沢賢治「虔十公園林」 [読書]
前回紹介した「グスコーブドリの伝記」について、多くの読者は、ブドリの数奇な運命とそのヒロイックな死のゆえに、「とてもブドリのような生き方は自分には無理だ」と思うかもしれない。しかし、何も他人を助けよう、英雄的な行いをしようと身構える必要はない。他人に迷惑をかけず、自分のやりたいことをやるという生き方で十分かもしれない。結果的に、それで人を喜ばすこともある。ちくま文庫「宮沢賢治全集第6巻」に所収された「虔十公園林」は、そんな物語だ。
虔十(けんじゅう)は、「いつも縄の帯をしめてわらって杜(もり)の中や畑の間をゆっくり歩いている」青年だった。彼は周りからは知恵遅れと見られていて、ほかの子供たちからも馬鹿にされていた。そんな虔十が、ある日突然、母親に「お母(があ)、おらさ杉苗七百本、買って呉(け)ろ」と頼み込む。家の後ろに運動場ぐらいの野原がまだ畑にならず残っていたのだが、そこに植えるのだという。父親は、虔十がこれまで何一つ頼みごとをしたことがなかったので、買ってやることにした。
その野原は土質が悪く、杉が育つはずはないと馬鹿にする者もいたが、やがて見事な杉並木に育っていき、子供たちの遊び場になる。虔十は子供たちが来ない雨の日もそこに立っていて、「今日も林の立ち番だなす」と通行人からからかわれた。
また、この野原の北側に畑を持つ平二というワルからは、自分の畑が日陰になるから杉を切れと言いがかりをつけられた。虔十は「伐らなぃ」と言い張る。「実にこれが虔十の一生の間のたった一つの人に対する逆らひの言(ことば)だった」という。虔十は、平二にボコボコにされたがじっと耐えた。そして、その秋、虔十はチブスで死に、平二もその10日前に同じ病気で死んだ。
その村はやがて鉄道が通り、町になって栄えたが、虔十の林はそのままだった。ある日、昔その村から出てアメリカのある大学の教授になった若い博士が15年ぶりに故郷へ帰ってきた。彼は母校の小学校で講演したあと、校長先生たちと運動場に出て、さらに隣接した虔十の林に向かう。
・「あゝ、こゝはすっかりもとの通りだ。木まですっかりもとの通りだ。木は却って小さくなったやうだ。みんんなも遊んでゐる。あゝ、あの中に私や私の昔の友達が居ないだらうか。」「こゝは今は学校の運動場ですか。」
・「いゝえ。こゝはこの向ふの家の地面なのですが家の人たちが一向かまはないで子供らの集まるまゝにして置くものですから、まるで学校の附属の運動場のやうになってしまひましたが実はさうではありません。」
・「それは不思議な方ですね、一体どう云うわけでせう。」
・「こゝが町になってからみんなで売れ売れと申したさうですが年よりの方がこゝは虔十のたゞ一つのかたみだからいくら困っても、これをなくすることはどうしてもできないと答へるさうです。」
・「ああさうさう、ありました、ありました。その虔十といふ人は少し足りないと私らは思ってゐたのです。いつでもはあはあ笑ってゐる人でした。毎日丁度この辺に立って私らの遊ぶのを見てゐたのです。この杉もみんなその人が植ゑたのださうです。あゝ全くたれがかしこくたれが賢くないかはわかりません。たゞどこまでも十力の作用は不思議です。こゝはもういつまでも子供たちの美しい公園地です。どうでせう。こゝに虔十公園林と名をつけていつまでもこの通り保存するやうにしては。」
賢治は、この小説の終わり近くで次のように書いている。「全く全くこの公園林の杉の黒い立派な緑、さはやかな匂、夏のすゞしい陰、月光色の芝生がこれから何千人の人たちに本当のさいはひが何だかを教へるか数へられませんでした。」
× × ×
私は、この小説を読むたびにいつも深い感慨を覚える。
宮沢賢治「グスコーブドリの伝記」 [読書]
宮沢賢治の小説「グスコーブドリの伝記」をもとにしたアニメ映画が昨日公開されたようだ。ここのところ以前からため込んでいた仕事に加え、急に入ってきた仕事もあり、当面、観に行くことは難しそうだ。そこで、映画の代わりに小説を読んでみた。ちくま文庫「宮沢賢治全集」の第8巻に所収されている。私は、10年くらい前、骨折で病院に1ヵ月間入院したとき、「宮沢賢治全集」の第6巻、第7巻、第8巻を読んでおり、今も手許に持っている。ただ、残念ながら内容は忘れてしまっていた。
小説の主人公は、グスコーブドリという。イーハトーブの大きな森の中に生まれ、お父さんは、グスコーナドリという名高い木樵り(きこり)で、お母さんと、ネリという3つ下の妹と一緒に暮らしていた。ブドリが10歳になったとき、この地方を冷夏が襲い、翌年も繰り返されて「ほんたうの飢饉」になってしまった。ある日お父さんは、森に出かけていき、帰ってこなかった。お母さんもその後を追って家を出て行き、帰ってこなかった。幼い子供を残して、自ら「口減らし」を決行したのだった。ブドリとネリは、お母さんが「お前たちはうちに居てあの戸棚にある粉を二人ですこしづつたべなさい」と言われたのにしたがい、何とか糊口をしのいだ。
20日ほどして、「この地方の飢饉を救けに来た」と名乗る見知らぬ男が訪ねてきて、ネリをさらっていく。一人残されたブドリは、「てぐす工場」を始めた男と出会う(「てぐす」とは、ヤママユガ科のテグスサンという昆虫の幼虫からとった絹糸腺を酸で処理して作った釣り糸のこと)。この男は、自分は森全体を買い取ったと言い、ブドリたちが住んでいた家も「てぐす工場」にされてしまっていた。ブドリはこの男のもとで働くが、1年と続かなかった。地震と噴火によって、てぐす事業の存続が不可能になったからだ。
ブドリは森を抜け出し、今度はオリザ(イネ属の植物)栽培農家の赤髭の男のもとで6年間働く。この主人は山っ気の多い人物だが、人情家でもあった。ある日、ブドリにこう言う。「ブドリ、おれももとはイーハトーブの大百姓だつたし、ずゐぶん稼いでも来たのだが、たびたびの寒さと旱魃(かんばつ)のために、いまでは沼ばたけも昔の三分の一になつてしまつたし、来年は、もう入れるこやしもないのだ。・・・おまへも若いはたらき盛りを、おれのとこで暮らしてしまつてはあんまり気の毒だから、済まないがどうかこれを持つて、どこへでも行つていゝ運を見つけてくれ。」「これ」というのは、「一ふくろのお金と新しい紺で染めた麻の服と赤革の靴」だ。
これが、ブドリの人生の転機となる。彼は、イーハトーブ市にやってきて、そこでかねてより会いたいと思っていたクーボー大博士と出会う。学校に行き、そこでクーボー先生の授業を押し掛けで聴講したのだ。講義終了後、学生たちは先生にノートを示し、質問に答え、評価してもらうのだが、最後にブドリの順番が来た。先生は、「よろしい。この図は非常に正しくできてゐる」と、まずノートの出来映えを褒めた上で、いくつか質問する。
・「工場の煙突から出るけむりには、どういふ色の種類があるか。」
・「黒、褐、黄、灰、白、無色。それからこれらの混合です。」
・「無色のけむりは大へんいゝ。形について云ひたまへ。」
・「無風で煙が相当あれば、たての棒にもなりますが、さきはだんだんひろがります。雲の非常に低い日は、棒は雲まで昇つて行つて、そこから横にひろがります。風のある日は、棒は斜めになりますが、その傾きは風の程度に従ひます。波や幾つもきれになるのは、風のためにもよりますが、一つはけむりや煙突のもつ癖のためです。あまり煙の少ないときは、コルク抜きの形にもなり、煙も重い瓦斯がまじれば、煙突の口から房になって、一方乃至(ないし)四方に落ちることもあります。」
・「よろしい。きみはどういふ仕事をしてゐるのか。」
・「仕事をみつけに来たんです。」
博士は大いにブドリが気に入り、「面白い仕事がある。名刺をあげるから、そこへすぐ行きなさい」と言って、イーハトーブ火山局の仕事を世話する。ブドリを迎えてくれたのは、火山局の老技師ペンネンナームで、仕事についてこう説明する。「ここの仕事は、去年はじまつたばかりですが、じつに責任のあるもので、それに半分はいつ噴火するかわからない火山の上で仕事するものなのです。それに火山の癖といふものは、なかなか学問でわかることではないのです。われわれはこれからよほどしつかりやらなければならんのです。」
ここでちょっと脱線することをお許し戴きたい。先週、私が担当する学部学生のゼミで、警察官にふさわしい人を採用するには、どのような筆記試験や面接試験を行ったらよいかというケース素材を扱った。専門用語でいうと採用試験の「妥当性」(validity)いかんという問題だ。私は、クーボー大博士がブドリに対して行った質問ほど、火山局の技師としての適性を見極めるのにふさわしい質問はないと感心した。ブドリの答えは、自然現象を常日頃よく観察し、それを体系化、知識化している者でなければ出てこない。その前提として、自然そのものに対する興味や根気強さも必要だ。
話を元に戻す。ブドリは火山局で水を得た魚のように働く。行方不明だった妹のネリとも再会した。彼女はある親切な牧場主に拾われ、そこの息子と結婚したのだった。ところが幸せは長く続かない。ブドリが27歳になったとき、恐ろしい冷夏が再来しそうな様子になった。「このままで過ぎるなら、森にも野原にも、ちやうどあの年のブドリの家族のやうになる人がたくさんできるのです。ブドリはまるで物も食べずに幾晩も幾晩も考へました。」
ブドリはクーボー大博士に相談する。気層にCO2が増えれば暖かくなるか、カルボナード火山島を爆発させたら十分なCO2を出せるかと。
・「先生、あれを今すぐ噴かせられないでせうか。」
・「それはできるだろう。けれども、その仕事に行つたもののうち、最後の一人はどうしても遁げられないのでね。」
・・・
物語は次のように終わる。「そしてちやうど、このお話のはじまりのようになる筈の、たくさんのブドリのお父さんやお母さんは、たくさんのブドリやネリといつしよに、その冬を暖かいたべものと、明るい薪で楽しく暮らすことができたのでした。」
× × ×
何と悲しく、温かく、崇高な物語だろうか。3.11のとき、役場にとどまって津波避難のアナウンスを続けたため、津波にさらわれてしまった若い女性がいた。ほかにも多くの「ブドリ」がいた。みんな「命を懸けて」などとかっこつけた台詞を吐く間もなく、逝ってしまった。
坂口安吾「日本文化私観」 [読書]
私が、坂口安吾を本格的に読んだのは30代の前半、アメリカの大学院で博士論文を書いていた時期だ。その大学は、ニューヨーク州の真ん中あたりにあり、東海岸のニューヨーク・シティまでクルマで片道6時間くらいかかった。年に2、3回、日本食品や日本の本などを買いに出かけたが、あるとき本屋で偶然買ったのが、安吾の「日本文化私観」や「堕落論」などを収めた文庫本だった。あまりにおもしろく、一気に読んだのを覚えている。中学や高校の時、定期試験が近づくと、試験勉強とは関係のない小説を無性に読みたくなったりしたが、博士論文執筆のストレスからの逃避もあったかもしれない。
その後、1冊だけでは終わらず、結局、ちくま文庫から出ていた「坂口安吾全集全18巻」を全て買い、その大半を読んだ。個人の全集を買いそろえたのは、後にも先にも安吾だけである。
私は、この才気煥発、多才な作家のさまざまな作品が好きだが、どれか一つ挙げろと言われたら、「日本文化私観」(1942年)だ。
・「僕は日本の古代文化に就いて殆ど知識を持っていない。・・・けれども、そのような僕の生活が、祖国の光輝ある古代文化の伝統を見失ったという理由で、貧困なものだとは考えていない」(「坂口安吾全集第14巻」ちくま文庫、p. 352)。このエッセイの冒頭、安吾らしい皮肉混じりの挑発的な文章で始まる。
・「多くの日本人は、故郷の古い姿が破壊されて、欧米風な建物が出現するたびに、悲しみよりも、むしろ喜びを感じる。新しい交通機関も必要だし、エレベーターも必要だ。伝統の美だの日本本来の姿などというものよりも、より便利な生活が必要なのである。京都の寺や奈良の仏像が全滅しても困らないが、電車が動かなくては困るのだ。我々に大切なのは「生活の必要」だけで、古代文化が全滅しても、生活は亡びず、生活自体が亡びない限り、我々の独自性は健康なのである」(p. 356)。戦中に書かれた文章だが、戦後にも通じる日本人の「近代」志向を言い当てている。私は、ヨーロッパの街をあちこち歩いて、彼らがいかに旧いもの(街並み、建物、生活様式・・・)を大切にしているか、正直驚いた。
・「伝統の貫禄だけでは、永遠の生命を維持することはできないのだ。・・・貫禄を維持するだけの実質がなければ、やがては亡びる外に仕方がない。問題は、伝統や貫禄ではなく、実質だ」(p. 362)。この指摘も小気味よい。
・「まっとうでなければならぬ。寺があって、後に、坊主があるのではなく、坊主があって、寺があるのだ。寺がなくとも、良寛は存在する。若し、我々に仏教が必要ならば、それは坊主が必要なので、寺が必要なのではないのである。京都や奈良の古い寺がみんな焼けても、日本の伝統は微動もしない。日本の建築すら、微動もしない。必要ならば、新たに作ればいいのである。バラックで、結構だ」(p. 375)。「必要ならば、新たに作ればいい」というフレーズは、この後ずっと私の耳に残った。
・「見たところのスマートだけでは、真に美なる物とはなり得ない。すべては、実質の問題だ。美しさのための美しさは素直でなく、結局、本当の物ではないのである。要するに、空虚なのだ。そうして、空虚なものは、その真実のものによって人を打つことは決してなく、詮ずるところ、有っても無くても構わない代物である。法隆寺も平等院も焼けてしまって一向に困らぬ。必要ならば、法隆寺をとりこわして停車場をつくるがいい。我が民族の光輝ある文化や伝統は、そのことによって決して亡びはしないのである」(p. 384)。「必要」や「実質」こそが「美」の源泉であり、それこそが本物の「文化」だ、というのが安吾の主張である。
私は、このエッセイのどこに惹かれたのだろうか? いくつかの理由が考えられる。一つは、そのころ、私が10年近いサラリーマン生活に一区切りをつけ、研究者を目指すというキャリア転換の最中にあったことだ。不安だが楽しい毎日だった。自分がしたいことに正直でありたい、世間的な安定などは二の次だという気持ちは、安吾の言う「必要」や「実質」と共鳴しあうと感じた。
もう一つ、私の当時の研究テーマである経済学の新制度派的なアプローチとも相通じるものを感じた。アメリカを中心とした経済学の主流は「新古典派」(neo-classical)と呼ばれ、個人の合理的選択、市場メカニズムの効率性などを分析の柱としている。これに対し、「制度派」(institutional)と呼ばれる少数派は、個人の行動は必ずしも合理的ではないし、市場メカニズムだけが資源配分の支配的な形態ではない、歴史的に形成される組織や制度の役割をもっと重視すべきであると主張する。
これらに対し、1980年代に登場したいわゆる「新制度派」(neo-institutional)は、新古典派からの制度派に対する逆襲といった側面を持つ。彼らは、制度派が重視する組織や制度は必ずしも市場メカニズムと対立するものではなく、(一定の条件下で)効率性を実現するための補完的な仕組みであると主張する。また、個人の合理的選択は、新古典派と同様、基本前提として維持する。つまり、非合理的、非効率的と見なされがちな非市場的な制度を、合理性や効率性の観点から再解釈しようとするのである。
一応、以上の予備知識を前提に、ここでは新制度派と安吾の主張の間にある親和性についてのみ、簡単に説明しておこう。新制度派的な考えを「文化」に適用するとどうなるか。文化(というある種の制度)は経済の枠外にあるものではない、個人が合理的な選択を行い、社会全体にとって効率的な資源配分をもたらすように形成されるものだ、もしそれに反するようなものであるなら、そうした文化は淘汰され死滅するだろう、ということになる。
その後、私のものの考え方のどこかには、効率的でない制度や文化はどんどん潰してしまえばよい、もしも潰して問題があるのならまた作ればよい、という過激というか乱暴な思想がある。一度、同僚だったH先生にこうした議論をぶつけたことがあるが、彼は私の考えには反対だと言っていた。H先生が予想外に若くして急逝してしまったため、その後議論できなくなったのが残念だ。
今になって考えると、安吾の主張も新制度派の考えも、ある種の極論だ。一度潰したものは、それが貴重なものであればあるほど、簡単に元には戻らない。個人の合理性(短期的な損得勘定のこと)だけで、簡単に何でも潰してしまってよいものかどうか。原発事故地域のように、戻そうにも半永久的に戻せないものもある。ただ、若いころに出会った思想を完全に払拭するのは難しい。皮肉なことに、そのこと自体、新制度派の主張と矛盾がある。
*冒頭の写真は、鎌倉鶴岡八幡宮の大銀杏の切り株(親木)。2010年3月10日未明の強風で倒伏し、親木は元の場所から左側に移植された。幹から新たに芽が出て葉が付いている(写真の真ん中より上、左と右に注目されたい)。下の写真は、元の場所に残された根から出てきた櫱(ひこばえ)。保護シートが上を覆い、大事にケアされている。われわれが、大銀杏の再生にここまで努力するのはなぜだろうか。
島尾敏雄「春の日のかげり」 [読書]
男性心理の「分析」ということで言えば、忘れがたい思い出がある。高校時代、現代国語の教科書に島尾敏雄の「春の日のかげり」という短編小説が載っていた。あまりに思い出深く、30代のころ、ちくま日本文学全集(文庫版)の一冊として『島尾敏雄』を買い求め再読したことがある。彼の「出発は遂に訪れず」などもよいが、やはり「春の日のかげり」は思い出深い。
小説のあらすじはこうである。主人公の「私」は、長崎の学校の柔道部員だ(注:作者の島尾敏雄自身、長崎高商で学んでいる)。「ある春先のうららかな日曜日に」、私は柔道部のレクレーションで唐八景(注:長崎市の東南部にある眺望のよい公園)にピクニックに出かけた。そこで、部員たちは遠くに二人の若い娘を見つける。キャプテンが「突撃!」と叫び、みんな彼女たちに向かって駆けだした。気がつくと、キャプテンと私だけが先頭を切って走っており、ついに私は一人の少女に追いつく。
「自分をけしかけて、思い切って、少女の丸っこい肩をわし掴みにして、それでも、すぐうしろから来るに違いないキャプテンに、えものを差し出す、すがりつくような気持ちで、にこにこした表情を無理に作って振り向くと、何としたことか、他の者の姿はおろか、一緒に走って来たと思ったキャプテンまでが、岩乗な背中を見せて、遠い感じで頂上近くにあたふたと戻って行くのを認めただけでした。」私と少女は、ぎこちない会話を二言、三言交わす。少女の方は、まんざらでもないというサインを送るのだが、私は冷静ではおられず、「少女にくるりと背を向けてしまうと、うしろ髪を引かれる思いで、仲間たちの方へ戻っていきました。」そのあと、若干の解説や後日譚が続くが、小説のクライマックスは、あくまでもここだ。
この小説の何が思い出深いかというと、教科書に「『私』が仲間たちの方へ戻って行ったのはなぜですか。そのときの『私』の気持ちを説明しなさい」という質問が載っていて(似たような別の質問だったかもしれない)、それに対するクラスのAさんという女生徒の答えが実にショッキングだったことだ。彼女が、先生から指名されて答えたのか、自分から手を挙げて答えたのかは覚えていない。さらに言えば、彼女が何と答えたかも忘れてしまった。しかし、よく覚えているのは、彼女の答えが、あまりに男心の深層に立ち入ったもので、男である私でも、とても思いつかないようなものだったこと、そして、そのことに私が非常に衝撃を受けたという事実だ。
彼女は、学年でも評判の美人で、カレ氏もおり、おませな生徒だったということもあるかもしれない。しかし、それにしても、何で、そんなに男心を見透かしたようなことが言えるんだ、と私はショックを受けた。半ば感嘆、半ば憤激だったかもしれない。一方、私はと言えば、女性とつき合ったこともなく、女心など、高等数学以上に難解だった。実際、現代国語の成績はつねに数学より悪く、特に「文中の〇〇の気持ちとして最も近いものを次の中から選びなさい」などという質問は、半分以上の確率で不正解だった。
50代半ばの今になって、「春の日のかげり」を再々読し、上の質問に答えてみようとしたが、やはり高校時代から何の進歩もないようだ(笑)。あれから、人並みの人生経験は積んでいるはずなのに・・・。でも、今なら、もう少し自信を持って言える。人間の心の中なんて、そんなに簡単に言えるものなのか、と。ユゴーも言っているではないか。「人の魂の内部は海よりも、空よりも大きく、これ以上、恐ろしくて、複雑で、神秘で、無限なものはない」と(2012年3月5日付、本ブログ)。
太宰治「新樹の言葉」 [読書]
私は太宰の熱心な読者であったことはないが、彼の文章力、とりわけ比喩表現の巧みさにはしばしば感心する。例えば、この小説の冒頭で彼は、甲府のことを次のように表現する。
「甲府は盆地である。四辺、皆、山である。小学生のころ、地理ではじめて、盆地という言葉に接して、訓導からさまざまに説明していただいたが、どうしても、その実景を、想像してみることができなかった。甲府へ来て見て、はじめて、なるほどと合点できた。大きい大きい沼を、搔乾(かいぼし)して、その沼の底に、畑を作り家を建てると、それが盆地だ。・・・沼の底、なぞというと、甲府もなんだか陰気なまちのように思われるだろうが、事実は、派手に、小さく、活気のあるまちである。よく人は、甲府を、『擂鉢の底』と評しているが、当っていない。甲府は、もっとハイカラである。シルクハットを倒(さか)さまにして、その帽子の底に、小さい小さい旗を立てた、それが甲府だと思えば、間違いない。きれいに文化の、しみとおっているまちである」(『太宰治全集2』ちくま文庫、pp. 267-268)。
この小説自体は短く、ストーリーも他愛ないと言えば他愛ない。東京での生活に倦んで甲府にやってきた主人公、青木大蔵が、内藤幸吉と名乗る若者と偶然出会う。その若者は青木に対して、津軽であなたの乳母をしていた女性の息子だと名乗り、青木も記憶がよみがえる。その乳母をしていた女性、つるは、乳母を辞めた後、甲州の甲斐絹問屋の番頭のところに嫁ぎ、一男一女をもうけたのだった。夫は、やがて独立して甲府で呉服屋をはじめたが、つるは若くして死んでしまい、呉服屋は傾き、夫は自殺し、二人の子供が残された。
幸吉は、出会った日に青木を立派な料亭に誘う。それは、かつて自分が生まれ育った呉服屋の建物に他ならない。青木はすっかり酔っ払って悪態をつく。
「私が大学の先生くらいになっていたら、君は、もっと早く、私の東京の家を探し出して、そうして、君は、君の妹さんと二人で、私を訪ねて来た筈だ。いや、弁解は聞きたくないね。ところが私は、いま、これときまった家さえない、どうも自分ながら意気地のない作家だ。ちっとも有名でない」(p. 285)。
「『しょげちゃいけない。いいか、君のお父さんと、それから、君のお母さんと、おふたりが力を合わせて、この家を建設した。それから、運がわるく、また、この家を手放した。けれども、私が、もし君のお父さん、お母さんだったら、べつに、それを悲しまないね。子供が、二人とも、立派に成長して、よその人にも、うしろ指一本さされず、爽快に、その日その日を送って、こんなに嬉しいことないじゃないか。大勝利だ。ヴィクトリィだ。なんだい、こんな家の一つや二つ。恋着しちゃいけない。投げ捨てよ、過去の森。自愛だ。私がついている。泣くやつがあるか。』 泣いているのは私であった」(pp. 285-286)。
それから二日後の夜中、火事があった。青木が城跡の高台まで上って見下ろすと、燃えているのは例の料亭だった。とんと肩をたたかれ振り向くと、幸吉兄妹だった。「あ、焼けたね。」「ええ、焼ける家だったのですね。父も、母も、仕合わせでしたね。」
小説の最後は、青木のつぎの言葉で結ばれている。「君たちは、幸福だ。大勝利だ。そうして、もっと、もっと仕合わせになれる。私は大きく腕組みして、それでも、やはりぶるぶる震えながら、こっそり力こぶいれていたのである」(p. 291)。
今日は、卒業式ということもあって、この小説を思い出した。太宰に代わって、私からも卒業生諸君にひとこと言おう。「困難な時代に巣立つ君たちは大変だと思う。でも、かつてより恵まれていることもたくさんある。いずれにせよ、君たちは若い。それだけでも大勝利だ。Bravo! Bon courage!」
*写真は、甲府の山梨県立美術館にて。富士山がかすかに、爪先程度のぞいている。
カズオ・イシグロ「日の名残り」 [読書]
パリのフランス語学校に通っていたとき、ひょんなことから話題が英仏の貴族制度比較論になった。そのとき、フランス人の先生が薦めてくれた小説(そして映画)がカズオ・イシグロの「日の名残り」(The Remains of the Day)だった。ヨーロッパ滞在中、カズオ・イシグロの愛読者だという人に、(アメリカ人も含め)何人か出会った。ひょっとしたら村上春樹より有名かもしれない。
私は、カズオ・イシグロという名前を聞いたことはあったが、その作品は読んだことがなかった。さっそくアマゾンから購入して読んでみた。土屋政雄氏の日本語訳には定評があるが、なるほど優雅で読みやすく、内容もとても面白かった。
大まかなあらすじを言うと、イギリスのある有力な貴族(ダーリントン卿)に執事として長年仕えた主人公(スティーブンス)が、第2次大戦後、新しい主人から休暇を取ってはどうかと勧められ、貴族の館ダーリントン・ホールから、港町ウェイマスまで自動車旅行に出かける。その途中、さまざまな人に出会っていろいろと考えたり、また過去の思い出話を語ったりしていくという内容である。
私が、特に面白く感じた点をいくつか、以下に記しておきたい。
第一。主人公の執事は、「偉大な執事とは何か」という問をずっと考え続けてきた。「一日の仕事が終わったあと、召使い部屋の火を囲みながら、この問題を飽きずに何時間でも論じ合ったことを思い出します」という(ハヤカワ文庫版、p. 42)。この話を印象深く感じたのは、私にも似たような経験があるからだ。私が今の職場に来たとき、KK先生という偉大な先生がおられ、同僚のKT先生やSH先生とともに何度も一緒に飲んだり、お宅に呼んでいただいたりしたことがある。そのときの話題の多くが、誰が偉大な学者かという人物月旦だった。
スティーブンスがたどり着いた結論は「品格(dignity)」である。「では、『品格』とは何なのか。じつは、ミスター・グレアムらと私が、夢中で論じ合った問題の一つがこれでした。ミスター・グレアムはいつも、品格とはご婦人の美しさのようなもので、分析は無意味だと言っておりました。しかし、私は反対でした。そのようなたとえは、ミスター・マーシャルらの品格を軽んずることになると思いましたし、それに、その考え方を突き詰めていくと、品格の有無は自然の気まぐれで決まってしまうことになります。醜いご婦人がいくら努力しても美しくはなれないように、初めから品格を持っていない人は、いくらそれを身につけようと努力しても、結局は無駄ということになってしまいます。たしかに、執事の大半は、いろいろやってみても、結局、自分は駄目だったと悟らざるをえないのかもしれません。が、それはそれとして、生涯かけて品格を追求することは、決して無意味だとは思われません」(pp. 48-49)。「品格の有無を決定するものは、みずからの職業的あり方を貫き、それに堪える能力だと言えるのではありますまいか。並の執事は、ほんの少し挑発されただけで職業的あり方を投げ捨て、個人的なあり方に逃げ込みます。・・・偉大な執事が偉大であるゆえんは、みずからの職業的あり方に常住し、最後の最後までそこに踏みとどまれることでしょう。外部の出来事には-それがどれほど意外でも、恐ろしくても、腹立たしくても-動じません」(p. 61)。ちなみに、KK先生も、時流に迎合して要領よくスタンスを変える学者はひどく嫌っておられた。
第二。スティーブンスと女中頭のミス・ケントンとの間ですれ違う(恋愛)感情である。お互い、些細なことで突っ張り合ってしまう。これは映画版では主要なモチーフとして取り上げられているが、私はあまり賛成できない。ここでは単にそのことを指摘するにとどめる。
第三。執事は主人にいかに仕えるべきか。これは、一般のサラリーマン社会でも難問だ。スティーブンスはダーリントン卿に仕えた日々に関し、一点の曇りもなく誇らしく思っている。しかし、ダーリントン卿がナチスへの宥和政策に荷担したことに対し、イギリスでは戦後多くの非難が起こり、スティーブンスに対しても旅行中、そうした批判がぶつけられる。彼の信念はそれでも揺るがないのか?
小説の最後は、ウェイマスという海辺の町だ。ここで、スティーブンスはミス・ケントンと再会し、別れる。その二日後、桟橋前のベンチである男と一緒になる。その男は「夕方こそ一日でいちばんいい時間だ」と断言した。「人生、楽しまなくっちゃ。夕方が一日でいちばんいい時間なんだ」(p. 350)。そして、スティーブンスはこの男が去って20分後、つぎのように思った。
「人生が思いどおりにいかなかったからと言って、後ろばかり向き、自分を責めてみても、それは詮無いことです。私どものような卑小な人間にとりまして、最終的には運命をご主人様の-この世界の中心におれらる偉大な紳士淑女の-手に委ねる以外、あまり選択の余地があるとは思われません。それが冷厳なる現実というものではありますまいか。あのときああすれば人生の方向が変わっていたかもしれない-そう思うことはありましょう。しかし、それをいつまでも思い悩んでいても意味のないことです。私どものような人間は、何か真に価値あるもののために微力を尽くそうと願い、それを試みるだけで十分であるような気がいたします。そのような試みに人生の多くを犠牲にする覚悟があり、その覚悟を実践したとすれば、結果はどうであれ、そのこと自体がみずからに誇りと満足を覚えてよい十分な理由となりましょう」(pp. 351-352)。
ラストのシーンには加古隆の「黄昏のワルツ」が似合うと思う。そして、私も何だか力をもらったように感じた。
カミュ「ペスト」のパヌルー神父 [読書]
カミュの小説『ペスト』(La Peste)は、194x年、アルジェリアのオランを襲ったペストが人々にどのような影響をもたらしたか、特に何人かの主要登場人物が何を考え、どう振る舞ったかを描いた作品である。今回は、小説全体を通しての主人公とも言うべき医師のベルナール・リウー(Bernard Rieux)と、宗教家として小説中、特異な位置を占めるパヌルー神父(Père Paneloux)に注目したい。
イエズス会の情熱的な宣教師、パヌルー神父はミサで集まった聴衆につぎのように語りかける。
・「皆さん、あなたがたは禍のなかにいます。皆さん、それは当然の報いなのであります。」«Mes frères, vous êtes dans le malheur, mes frères, vous l’avez mérité.»
・「今日、ペストがあなたがたにかかわりをもつようになったとすれば、それはすなわち反省すべき時が来たのであります。心正しき者はそれを恐れることはありえません。しかし邪なる人々は恐れ戦(おのの)くべき理由があるのであります。」«Si, aujourd’hui, la peste vous regarde, c’est que le moment de réfléchir est venu. Les justes ne peuvent craindre cela, mais les méchants ont raison de trembler.»
こうしたパヌルー神父の説教に対して、リウー医師はつぎのような感想を抱く。
・「私はあんまり病院のなかでばかり暮らしてきたので、集団的懲罰などという観念は好きになれませんね。しかし、なにしろ、キリスト教徒っていうのは時々あんなふうなことをいうものです。実際には決してそう思ってもいないで。」«J’ai trop vécu dans les hôpitaux pour aimer l’idée de punition collective. Mais, vous savez, les chrétiens parlent quelquefois ainsi, sans le penser jamais réellement.»
・「パヌルーは書斎の人間です。人の死ぬところを十分見たことがないんです。だから、真理の名において語ったりするんですよ。しかし、どんなつまらない田舎の牧師でも、ちゃんと教区の人々に接触して、臨終の人間の息の音を聞いたことのあるものなら、私と同じように考えますよ。その悲惨のすぐれたゆえんを証明しようとしたりする前に、まずその手当てをするでしょう。」«Paneloux est un homme d’études. Il n’a pas vu assez mourir et c’est pourquoi il parle au nom d’une vérité. Mais le moindre prêtre de campagne qui administre ses paroissiens et qui a entendu la respiration d’un mourant pense comme moi. Il soignerait la misère avant de vouloir en démontrer l’excellence.»
ペストの猛威はその後も衰えず、罪のない子供たちの命も容赦なく奪う。パヌルー神父は保健隊に入り、ある少年の臨終にも立ち会うが、その様子にリウー医師は苛立ちを隠せない。ペストが人への懲罰だというのなら、どうして罪のない子供たちにその災禍が及ぶのだ、と。
・「まったく、あの子だけは、少なくとも罪のない者でした。あなたもそれはご存じのはずです!」«Ah ! celui-là, au moins, était innocent, vous le savez bien !»
・「子供たちが責めさいなまれるように作られたこんな世界を愛することなどは、死んでも肯(がえ)んじません。」«je refuserai jusqu’à la mort d’aimer cette création où des enfants sont torturés.»
・「人類の救済なんて、大袈裟すぎる言葉ですよ、僕には。僕はそんな大それたことは考えていません。人間の健康ということが、僕の関心の対象なんです。まず第一に健康です。」«Le salut de l’homme est un trop grand mot pour moi. Je ne vais pas si loin. C’est sa santé qui m’intéresse, sa santé d’abord.»
*冒頭の写真は、スイス、ルツェルンのシュプロイヤー橋にて。1635年に描かれたものとされ、ペストは幼児も容赦なく襲った。末尾の写真は、フランス、ランスのフジタ礼拝堂にて。フジタは第2次大戦後、子供を主題にした作品を好んで描いた。本ブログで、『ペスト』の日本語訳は宮崎嶺雄(訳)、新潮文庫(1969年)による。