ケネス・J.アロー『組織の限界』(岩波書店、1976年)(1) [経済]
ケネス・J.アローの『組織の限界』(岩波書店、村上泰亮訳、1976年)は、その後「組織の経済学」として発展した経済学の新しい領域について、早い段階で的確な見取り図を提示した好著だ。(原著の出版は1974年であり、内容は1970-71年に行われた講演録に基づいている。)特に1980年代以降、「組織の経済学」としてさまざまなモデルが生み出されてきたが、今、改めてこの本に立ち戻ってみる価値は大きいと思う。以下、かつての私の読書メモをもとに、その内容を簡単に要約してみたい。
* * *
○日本語版への序文
・ 「この本の内容は、むしろ一種の研究計画とみなしうるものであって、完了した仕事の成果ではないし、あるいは十分に展開された思考体系でさえもない」と断った上で、伝統的な経済学が「市場」を中心に扱ってきたこと、また「組織」を扱うにしても、市場の補足物として扱ってきたことに対して異議を唱える。
・ その第一の理由は、経済システムにおける決定単位の多くは個人ではなく組織だという事実認識である。第二に、市場はそれ自身、組織としての性格を数多く持つと指摘する。つまり、「市場」対「組織」という単純な二分法は必ずしも適切な分析枠組ではない。実際、全体としての社会は組織の最大のもの、という言い方もしている。
・ さらに、「正義の問題、社会的選択の問題は、組織理論の本来の一部である」とも言う。それは、「組織の機能が目的を共有するという感覚に依存し、そしてその目的が現に実現され理解されなければならない」からである。
第1章 個人的合理性と社会的合理性
・ 社会からの要求と個人からの要求の緊張は避けがたい、両者の合理的なバランスが理解されなければならないというのが本章のテーマだ。そのことを、アローは次のように表現する。「なんらかの形で、自分の内なる価値を表現しようとするのは、すべての個人の必然的欲求である。しかし社会の要求と、そしてまさしく社会の中においてのみ表現されうる個人の要求とは、個人が自分自身のためのみならず、他の人のためのものでもあることをもとめ、そしてまた、他の人を自分にとって手段であると同時に目的でもあるかのごとくみなすことを求める。」
・ そもそも人はなぜ集団的行動を取らなければならないのか、あるいは社会というものを持たなければならないのか。合理性を信奉する経済学者は、それは集団的行動によって個人的合理性の領域を拡張できるから、つまり、個人個人が、自分の個人的価値をいっそう十分に実現することができるようになるからだと考える。(非経済学者なら、集団的行動それ自体に情熱をかき立てるような意味があるからだと言うかもしれない。)
・ しかし、合理性はある目的が与えられたとき、どのような手段を選択するかという問題であって、目的の内容自体を特定することはできない。かくて究極的には、いかなる価値判断も分析不能な最終命題にたどり着き、そこでしばらく立ち止まらざるを得ない。
・ そう言った上で、アローは経済学者として言いうることをいくつか指摘する。まず、個人間の関係が、集団的な組織の一部として必要となる理由について。それは一つには、社会の基本的な資源の供給が制限されているため、競争を裁定するようなシステムが必要となることである。もう一つは、協力から発生する利益を確保するためである。
・ つぎに、さまざまな社会的組織をどう比較評価するかについて。経済学者は、効率性ないし最適性(より良い他の配分やシステムが存在しないということ)という概念を用いている。しかしこれは、最善の事態を一義的に定義するものではなく、さらなる比較のためには「分配上の正義」など他の基準を使わねばならない。
・ そして、価格システムの長所・短所について。まず、一般均衡理論モデルが証明したように(さまざまな前提を置いた上の話だが)効率性を達成できる。参加者に比較的わずかな知識しか要求しない。個人に自由の感覚が生まれる(しかしこの種の自由は所得がなければ幻想である)。利己主義を美徳化する(しかし、われわれは完全に利己的な動機に基づくシステムには不安を感じるのが常である)。いかなる形にせよ、公正な所得分配を与えるものではない。価格をつけられないものもある(水・大気汚染、信頼など)。これらから言えるのは、分配上の正義の観点のみならず、効率性の観点からも市場以上の何ものか(例えば政府)が求められているということである。
・ しかし、経済学者や倫理学者は、何らかの客観的な分配上の基準に到達しようと努めたが、結論に到達し得なかった。それは、人々の欲望や価値を同じ尺度で測ったり、相互に完全に伝達したりできないこと(the incommensurability and incomplete communicability of human wants and values)に由来する。「かくて、集団的合理性の意味は、完全に首尾一貫したものではあり得ない。」
・ 価格システムが、その内部では部分的に遮断されるもう一つの重要な領域は大企業である。企業とその被雇用者の関係は、対立的な契約関係とは非常に異なっている。「雇用契約は多くの点で、通常の財の契約とは異なっており、被雇用者は「権威」に喜んで従うという姿勢を売るのである。」
・ さらに目に見えない制度として、倫理や道徳の原則がある。社会はその進化の過程で、他人へ一定の配慮を払うことに関する暗黙の協定を発展させてきた。それは社会の存続に不可欠であり、効率性に大いに貢献する。
・ この章の結論は、おそらくアロー自身の次の言葉に込められている。いかなる瞬間においても、個人は必然的に彼の個人的欲望と社会の要求との間の対立に直面している。それゆえ、私は両者に完全な統一があり得るという観点を拒否する。われわれのとる価値は妥協の産物でなければならない。なぜなら、他人は自分と違った価値を持っており、いかなる社会的行動も何らかの共同や協定の要素を含んでいるからである。
第2章 組織と情報
・ 組織とは、価格システムがうまく働かないような状況の下で集団的行動の利点を実現するための手段と言える。
・ 組織を理解する上で絶対不可欠な点として、価格システムの一つの欠陥を指摘しておく。それは、不確実性の存在である。理論的には、あり得べき結果に対応して異なる条件で売買する契約(contingent commodity)を結べばよいが(保険はその一例である)、実際にはその応用は限られている。理由の第一は、価格のあり方が複雑になることであり、第二は、本当のリスクと単に最適な行動をとらなかったこととの区別をつけるのが難しいことである(いわゆるモラル・ハザード)。
・ 情報の非対称性といった「情報構造」は市場メカニズムの機能に大きく影響する。ここで、情報構造とは、任意の時点で現存している知識の状態に加え、将来において必要な情報を獲得する可能性(「情報チャネル」の獲得)を含んでいる。したがって、(市場ではなく)組織を作り出すことの望ましさは、ある程度までは情報チャネルの有無によって決まる。
・ ところで、情報チャネルの有無は経済システムにとって外生的なものではない。そこで、情報チャネルのコストについて検討しよう。まず、情報チャネルの設置、運用のためには個人自身が投入物である。そして、情報の獲得、処理を行う個人の能力は限られているため、情報の増加に対し収穫逓減(*)が生ずると予想される。
*岩波の日本語訳では「収穫逓増」となっているが(p. 40)、文脈からして「収穫逓減」の誤りである。実際、英文原著の表現も次の通りである。“one may expect a sort of diminishing returns to increases in other information resources”(p.39).
・ さらに、それらのコストは不可逆的な投資である。情報を獲得、処理するためには、時間や努力を十分に投資しておく必要がある。例えば、フランス語の情報を獲得、処理するには、フランス語を身につけておかねばならない。こうした特性の結果、情報投資は情報の価値がより不確実な場合には少なくなること、いったんある情報チャネルを獲得すると、別の情報チャネルへの乗り換えが困難になることが予想される。
・ 最後に、情報コストはさまざまな方向に不均一である。例えば、既に獲得した情報と近接した情報の獲得、処理は容易だが、そうでない情報の獲得、処理は困難を伴う。例えば、フランス語を習得した者にとってイタリア語やスペイン語の習得は容易なのに対し、日本語の習得は困難である。また、同じ文化や生活体験を持っている人の間の方が、そうでない人の間よりもコミュニケーションは容易であろう。
(次回に続く)
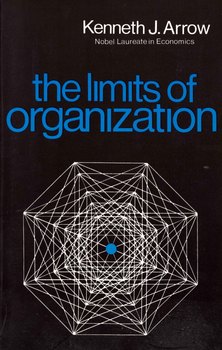




コメント 0