ケネス・J.アロー『組織の限界』(岩波書店、1976年)(2) [経済]
(承前)
第3章 組織の行動計画
・ 本章では、前章で取り上げた情報チャネルについて、その組織の中での役割をより具体的に議論している。そして、結論的には次の2つの含意を導いている。
①組織の現実の構造や行動は、偶然的事件、歴史に大きく依存するかもしれない。
②効率性のみの追究は、いっそうの変化に対する柔軟性と感応性の欠如につながるかもしれない。
・ 伝統的な経済学では、関連あるすべての変数の値が考慮されて意思決定が行われるものとされるが、実際には、そもそもどのような変数を認知すべきが難問である。その点を分析するため、組織にとって3つの意思決定領域があると仮定する。「活動中」(active)、「監視中」(monitored)、「非活動中」(passive)である。活動中とは、例えば、ある新規事業を行うべきかどうか具体的に検討されている、あるいは実行に移されているような領域、監視中とはいくつかの新規事業の候補が検討されているような領域、非活動中とはまだ具体的な検討対象に上がっていないような領域である。情報チャネルのコストという観点からすると、いったん活動中の領域に入った行動計画はそこから離れることは少なく、監視中の領域にある行動計画はそれと(情報面で)補完性がある場合が多いだろう。
・ 組織は、いかなる一人の個人よりも多くの情報を獲得できる。なぜなら、組織はおのおののメンバーに異なった「実験」(情報収集活動)を行わせることができるからである。しかし、情報が組織に役立つためには、相互に調整され関連させられなければならない。そして、情報の再伝達のためには、最終決定選択のための価値を失うことなしに、はるかに小さな容量に縮約されなければならない。このため、一般的には関連のある情報のすべてを伝達しない方が最適である。裏を返せば、個々のメンバーは、現在の状況では伝達に値すると判断できない情報(従って、組織としては非活動中の領域にある)を蓄積することになる。
・ 組織内のコミュニケーション・チャネルは、コスト最小の観点から設計される。その場合重要なのは、符号化様式(code)の適切な選択である。ここで符号化様式とは、情報伝達のためのあらゆる既知の手段のことを意味する。符号化様式は次の2つの経済的意味を持っている。①規模に伴うコスト増大傾向を弱めはするが、除去はできない。②個人にも組織にも不可逆性を作り出す(企業特殊的人的資本)。
・ ①に関して言うと、規模拡大によって組織が便益を受けるのは、そのメンバーに異なった実験をさせるからである。しかし、それはメンバーの専門化を促し、相互のコミュニケーションを困難にし、符号化様式の複雑化をもたらしてコスト増加につながる。②に関しては、メンバーは情報チャネルをある特定の組織の中で学び、それを通じて組織特有の符号化様式も学ぶことになる。そして、組織内に共通な符号化様式の採用は、組織参加者の行動に一様性の要請を課す。なぜ全ての企業が同一の符号化様式を持ち、その訓練が移転可能なものとならないのか。一つには、最適な符号化様式はそもそも数多く存在するからである。もう一つは、符号化様式は、それぞれの企業が作られた時点での最善の期待に合致するように定められ、その後の変更は困難になるからである(歴史が問題)。
・ 多くの点において、変化のコストは個人より組織にとって大きい。組織は、監視することに関しては多くの能力を持っているが、「非活動中」から「監視中」あるいは「活動中」に役割を切り替える能力は乏しい。しかし一方で、組織は変化する個人からなっている。個人が組織の外で教育を受けるなどして、組織は無料で相当量の情報を獲得できる。そのような無料の情報が十分なら組織の行動は変化する。一般的にいえば、組織設計における主要な要請は、大きな行動計画を取り扱う能力を増加させることであり、それには意思決定者の交代、「情報と意思決定ルールの循環」が必要となる。
第4章 権威と責任
(1)目標の対立
・ 組織では権威(authority)による配分が広く行われている。すなわち、ある個人によって行われた決定が、他の個人によって実行されている。
・ 権威には、人格的な権威(命令のやりとり)と非人格的な権威(事前に決められたルール、codes of conduct which prescribe what each member of the organization is to do under a variety of possible circumstances)がある。後者には結果の予想がつきやすいという利益があるが、柔軟性が失われるという不利益もある。
・ 権威の役割は組織によってさまざまであり、軍隊のように強いものから知的専門職の組織のように弱いものまである。雇用契約は、被雇用者の側において権威を受け入れるという契約に他ならない。この契約の範囲内では、雇用者と被雇用者の関係は市場的な関係ではなく、権威的な関係である。それは離職の自由によって制限されているが、離職にはコストがかかるから、権威の範囲は決してささやかなものでない。
・ 現在の世界においては、権威の衰退が傾向的に見られるが、そのことによって権威の源泉と必要性を再検討しようという傾向も強くなっている。権威に対して責任を課すべきだという主張が強まる一方、権威が必要だという感情も拡がっている。
(2)権威の価値
・ ホッブズは、権威が存在しないと「万人の万人に対する戦い」が起こるとしたが、より控え目にせよ、権威が必要なのは組織メンバーの活動を調整するためである。経済学的に言うと、権威とは意思決定の集権化であり、それによって情報の伝達・処理コストを節約できる。こうした権威の価値が最も純粋にあらわれる例は軍隊である。
・ 権威とは逆の極端な代案は合意(consensus)である。合意は、メンバーが全て同一の利害を持ち、かつ同一の情報を持っている組織では効率的であろう。(利害あるいは情報のいずれかが組織のメンバーの間で異なっているときには、合意を達成するためのコストが上昇する。)
(3)権威の達成
・ 権威は、何らかの権力を支配すること(control over some means of power)から生ずる。しかし、それは権威への服従の十分な説明ではない。制裁の存在は権威への服従の十分条件ではない。もしも、ある程度以上の数の従業員が命令に従わなければ、そのような命令は強制できない。
・ 結局のところ、権威は人々の期待の収束する焦点にとどまる限りにおいて持続しうるように思われる。ある個人が権威に従うのは、他の人々もそれに従うだろうと期待するからである。そのためには、権威を目に見えるものとし、シンボル化することが有益となる。もっとも、権威の源泉として期待の収束を強調すると、それは権威のもろさを意味することにもなる。
・ しかし、一方で権威をうみだそうとする圧力も強い。権威への服従が生ずるであろうという期待は、権威の維持にとって価値があるばかりでなく、権威に従う人々の不確実性を減少させるからだ。
(4)責任の価値
・ 責任を伴わない権威の基本的な欠陥は、不必要な誤りの可能性が高いことである。そのような失敗が起こるのは、権威者の情報上、意思決定上の容量の過大負担である。こうした問題は、権威者の先入観によって情報が濾過されがちであることによって、さらに増大する。
・ 一方、非人格的権威であるルールも、可能な事件の膨大な多様性に対して十分反応できない。ルールの形成に関して十分な柔軟性を達成するには、2つの決定的に重要な限界が存在している。
①あらゆる可能な事象を考慮することはコストが非常に高い。
②条件付きルールを具体的に施行するにも情報が必要となる。
したがって、自由裁量型権威から形式的ルールへの移行は万能でない。
・ これらのことは、権威を責任あるものに保つべき理由となる。すなわち、①情報の過大負担である。さらに、②絶対的かつ無責任な権威への服従自体が、従属者の成果に悪影響を与えるという議論もある(人間関係論など)。ただし、これは実証的根拠が乏しく、一方で、権威への憧れもある(フロム『自由からの逃走』)。(なお、アローは指摘していないが、③権威者の私利私欲という問題もある。)
(5)責任の達成
・ 責任の要素を含まない権威を想像することは、少なくとも長期的には困難である。なぜなら組織からの脱退は常に可能だし(ハーシュマン)、命令に対する不服従もありうるからだ。さらに、権威を行使する者を取り除くこともしばしば可能である。
・ これまでに責任達成のために用いられてきた構造的な手段の例としては、以下のものがある。
①より高い権威に対する責任(部長→社長)
②臨時的な権威に対する責任(社長→取締役会、株主)
③限定された分野でのみ正統性を持つ特殊な権威に対する責任(司法的権威)
④非権威的グループに対する責任(調査委員会、オンブズマン)
(6)権威と責任の間のトレードオフ
・ 責任メカニズムは誤りを修正できなければならない。しかし、それは権威の真の価値を破壊するようなものであるべきでない。そのためには、責任の取り方は時間的に非連続、あるいは周期的なものでなければならない。具体的には、誤りが起こったときに、それに関する非難を聴取するような再審査グループの提案である。その主要な機能は、情報の創出と組織内関係部署への伝達である。それには、再審査グループに一定の権威が必要であろう。
・ 「権威は、疑いもなく組織の目標を成功裡に達成するための必要条件である。しかしそれと同時に、権威は、制度的な構造の形に整備された再審査と公開の方式に対して責任をとらなければならないだろう。そうでなければ、思いがけぬ不服従の大波にさらされて、そのことの責任をとらなければならないことになるだろう」(p. 101)。
* * *
私は、以前この本を読んだとき、権威は責任をともなわなければならないが、そのことが絶え間ない権威の否定になってはいけないというアローの立場を、正直言って微温的に感じたことを告白せねばならない。しかし、権威の否定はアナキーにつながりかねず、さらに言えば、隠れた権威(例えばマスコミ?)の跋扈を許すことにもなりかねないと考えると、アローのいくぶん保守的な態度もそれなりに納得がいく。私がアローのガバナンス論に興味を持ったのは、私自身、ある組織のガバナンス論争に巻き込まれたことが機縁だったが、アローがこの本を書いた一つの背景に1960年代後半のハーバードにおける大学紛争があったようだ(訳本p. 100にごく短い記述がある)。そうした事情も踏まえて、特に第4章を読むとますます興味深い。
このほか、個人の要求と社会の要求のバランス、効率と公正の両方を考慮することなどバランス感覚に富んだ分析と、組織設計において大きな行動計画変更を可能にする世代交代のすすめなど大胆な提言がともに興味深かった。今後、よく反芻してみたい。
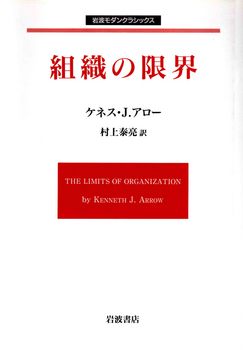




コメント 0